比較的マイナーな相振り四間飛車
相振り飛車戦では、四間飛車(第1図。先手四間飛車VS後手三間飛車の例)は三間飛車や向かい飛車に比べて損な戦法と言われています。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂v銀v金v玉v金v銀v桂v香|一 | ・ ・ ・ ・ ・ ・v飛v角 ・|二 |v歩v歩v歩v歩v歩v歩 ・v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・|五 | ・ ・ 歩 歩 ・ ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 ・ ・ 歩 歩 歩 歩 歩|七 | ・ 角 銀 飛 ・ ・ ・ ・ ・|八 | 香 桂 ・ 金 玉 金 銀 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=7 ▲6八飛まで
玉は深く3筋または2筋(場合によっては穴熊の1筋)に囲うのが一般的であり、三間飛車や向かい飛車なら相手玉に近いところで戦えるのに対し、四間飛車だと争点がズレがちだからです。

その代わり、6七(4三)の地点がしっかりと守られているので▲6五角(△4五角)を打たれる隙がなく、安定感があります(後述のように、三間飛車だと激しい変化がつきまといます)。
西川流
そんな風潮の中、純粋な四間飛車とは呼べませんが、西川和宏六段が編み出した「西川流」が四間飛車と向かい飛車を両天秤にかけたユニークなオープニング戦術として知られています。
初手から▲7六歩△3四歩▲6六歩と角道を止める手に対し、△3二飛と三間飛車にするのが後手の有力な戦術の1つですが、これに対し▲7七角と上がったあと飛車と左銀の移動を保留して8筋の歩をズンズンと伸ばしていくのが西川流です(第2図)。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂v銀v金 ・v金v銀v桂v香|一 | ・ ・ ・v玉 ・ ・v飛v角 ・|二 |v歩v歩v歩v歩v歩v歩 ・v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四 | ・ 歩 ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・|五 | ・ ・ 歩 歩 ・ ・ ・ ・ ・|六 | 歩 ・ 角 ・ 歩 歩 歩 歩 歩|七 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 飛 ・|八 | 香 桂 銀 金 玉 金 銀 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=9 ▲8五歩まで
このあと後手が動いてこなければストレートに向かい飛車、△3六歩▲同歩△同飛と動いてくれば▲6六飛(第3図)と四間飛車にします。
後手の持駒:歩 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂v銀v金 ・v金v銀v桂v香|一 | ・ ・ ・v玉 ・ ・ ・v角 ・|二 |v歩v歩v歩v歩v歩v歩 ・v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四 | ・ 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ 歩 歩 ・ ・v飛 ・ ・|六 | 歩 ・ 角 ・ 歩 歩 ・ 歩 歩|七 | ・ ・ ・ 飛 ・ ・ ・ ・ ・|八 | 香 桂 銀 金 玉 金 銀 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:歩 手数=13 ▲6八飛まで
西川流について詳しく知りたい方は、西川六段執筆の「これからの相振り飛車」をご覧ください。
2歩まとめて手持ちにする手筋
相振り飛車戦における四間飛車で有名な手筋は、6筋と8筋の歩をまとめて交換して手持ちにする手筋です。
例えば第4図。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂v銀v金 ・ ・ ・v桂v香|一 | ・ ・v玉 ・v金 ・v飛v角 ・|二 |v歩v歩v歩v歩v歩v銀 ・v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・ ・|四 | ・ 歩 ・ 歩 ・ ・v歩 ・ ・|五 | ・ ・ 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | 歩 ・ 角 ・ 歩 歩 歩 歩 歩|七 | ・ ・ 銀 飛 ・ 玉 ・ ・ ・|八 | 香 桂 ・ 金 ・ 金 銀 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=18 △4三銀まで
ここから▲8四歩△同歩▲6四歩(局面によって歩を突く順番で微妙なマギレが生じます)△同歩▲同飛△6三歩▲8四飛(第5図)で、2歩を手持ちにしつつ戦いやすい8筋に飛車を転換でき、一石二鳥です。
後手の持駒:歩 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂v銀v金 ・ ・ ・v桂v香|一 | ・ ・v玉 ・v金 ・v飛v角 ・|二 |v歩 ・v歩v歩v歩v銀 ・v歩v歩|三 | ・ 飛 ・ ・ ・v歩 ・ ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・|五 | ・ ・ 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | 歩 ・ 角 ・ 歩 歩 歩 歩 歩|七 | ・ ・ 銀 ・ ・ 玉 ・ ・ ・|八 | 香 桂 ・ 金 ・ 金 銀 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:歩二 手数=25 ▲8四飛まで
これが指したくて四間飛車にしている人もいるかもしれません。
石田流VS角道オープン四間飛車も
平成後期に入って一般的になってきたのが、角道オープン振り飛車です。それは相振り飛車の世界、そして三間飛車VS四間飛車の世界でも変わりません。
3手目▲7五歩に対する4手目△4二飛(第6図)。または初手から▲7六歩△3四歩▲6八飛(第7図)。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂v銀v金v玉v金v銀v桂v香|一 | ・ ・ ・ ・ ・v飛 ・v角 ・|二 |v歩v歩v歩v歩v歩v歩 ・v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・|四 | ・ ・ 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 ・ 歩 歩 歩 歩 歩 歩|七 | ・ 角 ・ ・ ・ ・ ・ 飛 ・|八 | 香 桂 銀 金 玉 金 銀 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=4 △4二飛まで
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂v銀v金v玉v金v銀v桂v香|一 | ・v飛 ・ ・ ・ ・ ・v角 ・|二 |v歩v歩v歩v歩v歩v歩 ・v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 ・ 歩 歩 歩 歩 歩 歩|七 | ・ 角 ・ 飛 ・ ・ ・ ・ ・|八 | 香 桂 銀 金 玉 金 銀 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=3 ▲6八飛まで
第6図は、先手が▲7五歩と突いているためすでに先手三間飛車VS後手四間飛車がほぼ確定。
第7図は、後手が望めば相振り飛車になります。例えば第7図以下△3二飛?!(第8図)または△3五歩で先手四間飛車VS後手三間飛車確定です。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂v銀v金v玉v金v銀v桂v香|一 | ・ ・ ・ ・ ・ ・v飛v角 ・|二 |v歩v歩v歩v歩v歩v歩 ・v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 ・ 歩 歩 歩 歩 歩 歩|七 | ・ 角 ・ 飛 ・ ・ ・ ・ ・|八 | 香 桂 銀 金 玉 金 銀 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=4 △3二飛まで
第8図は「▲6五角問題」(▲2二角成~▲6五角)が生じている危険極まりないオープニングですが、意外にバランスが取れています。詳しくは後述の「角交換相振り飛車 徹底ガイド」(杉本昌隆八段 著)をご覧ください。
関連棋書
先手三間飛車(石田流)で後手四間飛車を攻略する戦術を解説する棋書としては、「石田流を指しこなす本 相振り飛車編」(戸辺誠七段 著)がオススメです。VS角道クローズ四間飛車、VS角道オープン四間飛車の両方が載っています。
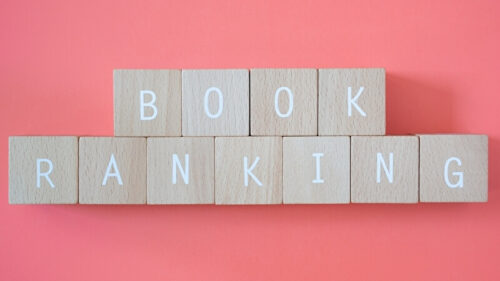
先手角道オープン四間飛車VS後手三間飛車については、「角交換相振り飛車 徹底ガイド」に詳しく載っています。
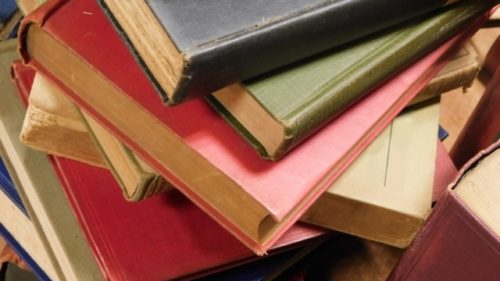
相振り四間飛車はメジャー化するか?
相振り飛車戦では、安定感はあるものの中途半端な布陣と見られがちな四間飛車。
西川流のような画期的な戦術が現れ、メジャーな戦法となる日がいつか来るでしょうか?
関連記事


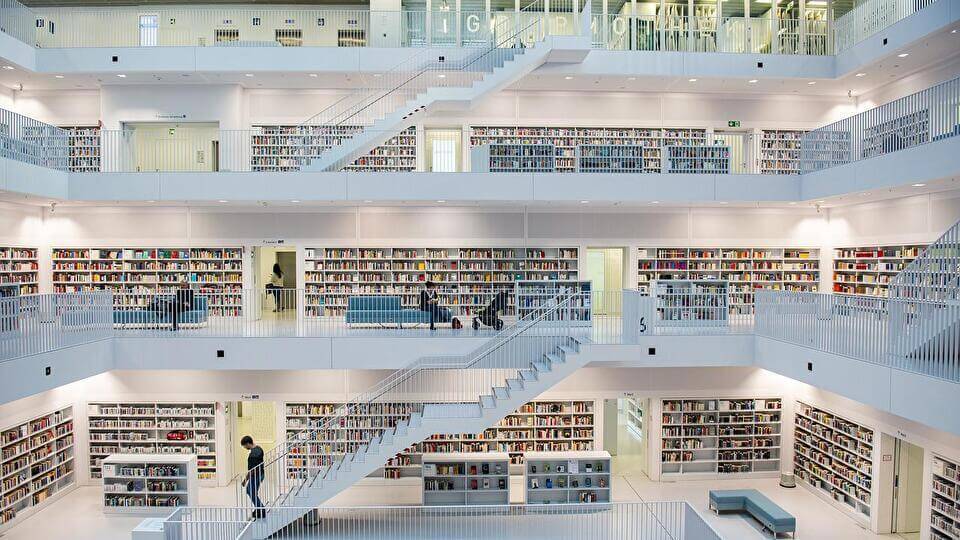
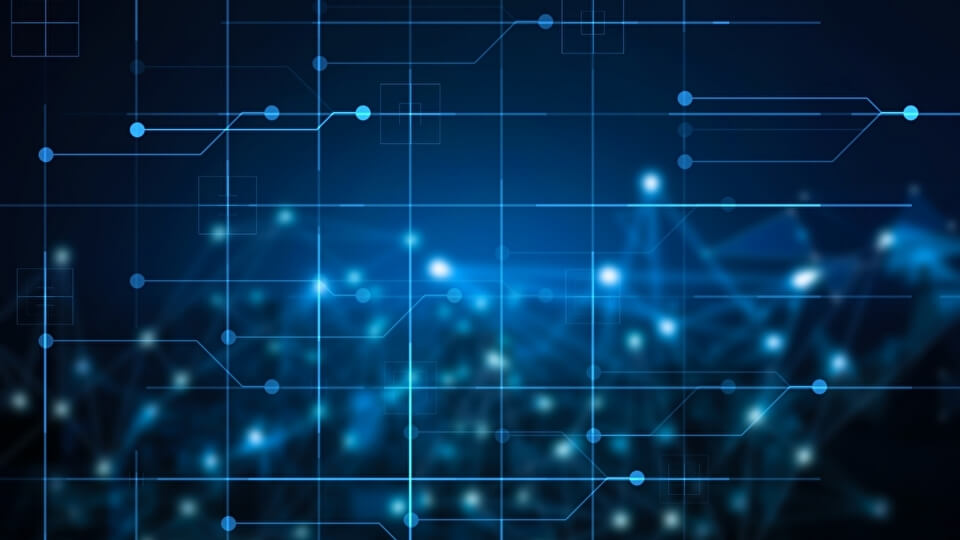
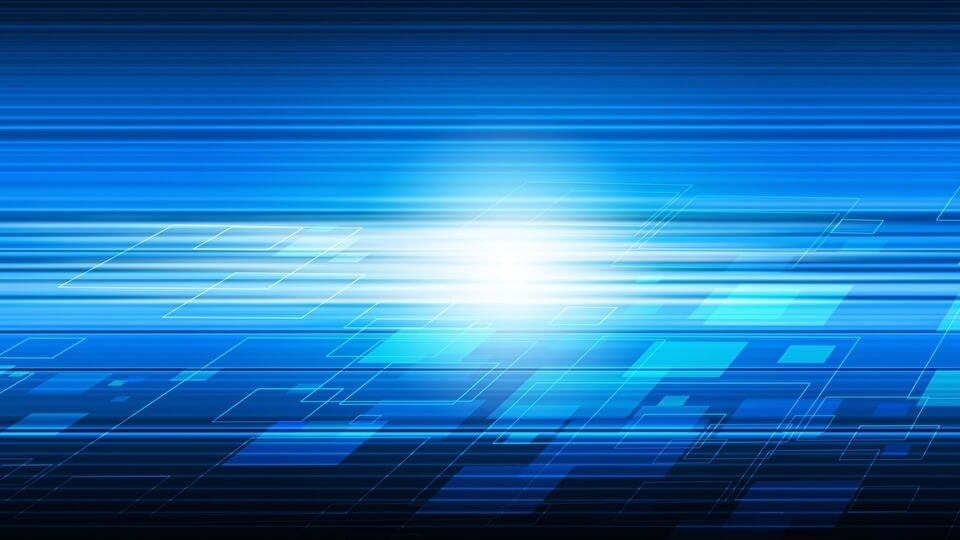
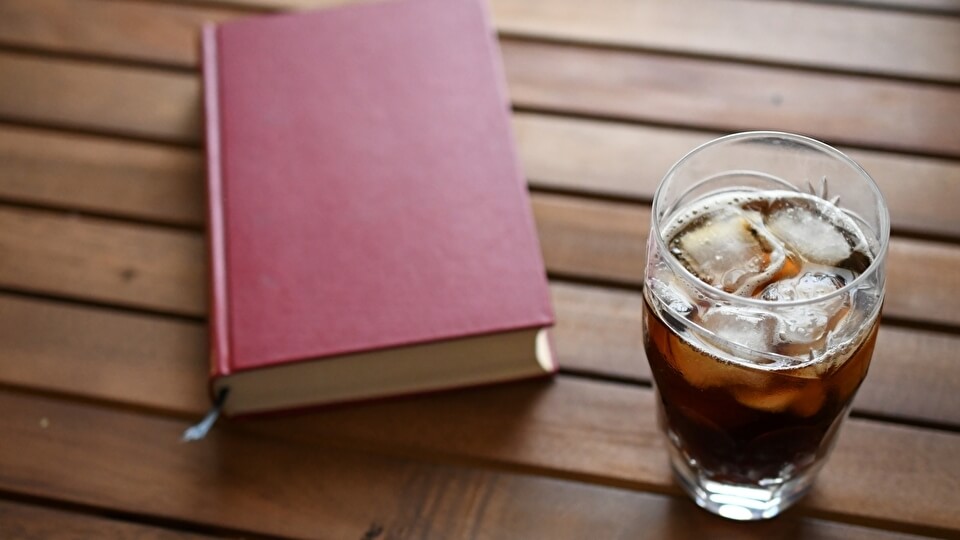










コメント