最速の▲4五歩早仕掛け
「いきなり早仕掛け」とは、三間飛車に対する▲4五歩早仕掛けの亜種の中でも最速の部類に属する急戦定跡です(第1図)。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂v銀v金 ・v金 ・v桂v香|一 | ・ ・ ・v王 ・v銀v飛 ・ ・|二 |v歩v歩v歩v歩v歩 ・v角v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・ ・v歩v歩 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・ 歩 ・|五 | ・ ・ 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 ・ 歩 歩 ・ 歩 ・ 歩|七 | ・ 角 ・ 王 ・ 銀 ・ 飛 ・|八 | 香 桂 銀 金 ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=0 ▲4五歩まで
本戦法を解説した将棋世界2010年11月号の付録「定跡次の一手 対後手三間飛車 いきなり早仕掛け」(将棋世界編集部 著)が名前の由来です。
アマチュア強豪の加部康晴氏が得意としていることから、「加部流」とも呼ばれています(後述の朝日オープンの記事より)。
三間飛車側の玉が7二に移動する前に仕掛けるのがポイントで、角交換後の▲6五角打が狙いのひとつです。
自陣が安定する前の仕掛けでハッとさせられますが、正しく対応すれば互角に戦えるとされています。
昭和の急戦定跡との比較
昭和時代に指された後手三間飛車に対するさまざまな居飛車急戦形のうち、平成時代にまで生き残ったのがいわゆる▲5七銀左型急戦(参考1図)と▲4五歩早仕掛け(参考2図)です。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・ ・ ・v桂v香|一 | ・v王v銀 ・v金v銀 ・v飛 ・|二 | ・v歩v歩 ・ ・ ・v角v歩v歩|三 |v歩 ・ ・v歩v歩v歩v歩 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・|五 | 歩 ・ 歩 ・ 歩 歩 歩 ・ ・|六 | ・ 歩 ・ 歩 銀 ・ 桂 ・ 歩|七 | ・ 角 王 ・ 金 銀 ・ 飛 ・|八 | 香 桂 ・ 金 ・ ・ ・ ・ 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=0 △6四歩まで
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂v銀v金 ・ ・ ・v桂v香|一 | ・v王 ・ ・v金v銀v飛 ・ ・|二 |v歩v歩v歩v歩 ・ ・v角v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・v歩v歩v歩 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・ 歩 ・|五 | ・ ・ 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ ・|六 | 歩 歩 ・ 歩 ・ ・ ・ ・ 歩|七 | ・ 角 王 ・ 金 銀 ・ 飛 ・|八 | 香 桂 銀 金 ・ ・ ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=0 ▲4五歩まで


▲5七銀左型急戦といえば参考1図の形にほぼ決まり(「▲5七銀左型」といえばこの舟囲いにほぼ限定されるため)ですが、一方で▲4五歩早仕掛けといえば参考2図と言えるほどには定跡は浸透していない上、戦法名が緩いため早めに▲4五歩と仕掛けたらなんでも▲4五歩早仕掛けと呼ばれている風潮があります。
そのため▲4五歩早仕掛けにはさまざまな亜種(左銀が6八に上がっていたり、5筋の歩を突いていなかったり)が存在しますが、そのうちのひとつがこの「いきなり早仕掛け」です。
取るや取らざるやの超急戦
前述の付録では、第1図から△4五同歩と取る手(第2図)と、△4三銀と上がる手(第3図)を解説しています。
後手の持駒:歩 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂v銀v金 ・v金 ・v桂v香|一 | ・ ・ ・v王 ・v銀v飛 ・ ・|二 |v歩v歩v歩v歩v歩 ・v角v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ 歩 ・|五 | ・ ・ 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 ・ 歩 歩 ・ 歩 ・ 歩|七 | ・ 角 ・ 王 ・ 銀 ・ 飛 ・|八 | 香 桂 銀 金 ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=0 △4五同歩まで
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂v銀v金 ・v金 ・v桂v香|一 | ・ ・ ・v王 ・ ・v飛 ・ ・|二 |v歩v歩v歩v歩v歩v銀v角v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・ ・v歩v歩 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・ 歩 ・|五 | ・ ・ 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 ・ 歩 歩 ・ 歩 ・ 歩|七 | ・ 角 ・ 王 ・ 銀 ・ 飛 ・|八 | 香 桂 銀 金 ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=0 △4三銀まで
また、第1図にいたる前に△4二銀ではなく△7二玉と寄った後手陣に対し▲4五歩と仕掛ける形(第4図)も解説しています。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂v銀v金 ・v金v銀v桂v香|一 | ・ ・v王 ・ ・ ・v飛 ・ ・|二 |v歩v歩v歩v歩v歩 ・v角v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・ ・v歩v歩 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・ 歩 ・|五 | ・ ・ 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 ・ 歩 歩 ・ 歩 ・ 歩|七 | ・ 角 ・ 王 ・ 銀 ・ 飛 ・|八 | 香 桂 銀 金 ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=0 ▲4五歩まで
狭く深く解説されていますが、形勢判断だけを引用すると、三間飛車側から見て△4五同歩よりも△4三銀のほうが勝るとしており、また△7二玉型だと居飛車の攻めが決まるとしています。
△4二銀は玉の移動の前に上がるのが普通なので、第4図を迎えることは稀でしょう。問題は△4五同歩か△4三銀か、です。
△4五同歩の変化
△4五同歩の変化で参考になるのが、2010年12月に行われた第4回朝日杯オープン戦、▲阿久津主税七段 対 △行方尚史八段戦です(参考3図)。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・v金v銀v桂v香|一 | ・v飛 ・v銀 ・v王 ・v角 ・|二 |v歩 ・v歩 ・v歩v歩 ・v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・|四 | ・v歩 ・v歩 ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ 歩 歩 ・ ・ ・ ・ 歩|六 | 歩 歩 角 ・ 歩 歩 歩 歩 ・|七 | ・ ・ 飛 銀 ・ 王 ・ ・ ・|八 | 香 桂 ・ 金 ・ 金 銀 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=0 △6五歩まで
本譜の棋譜と詳しい解説は、下記の朝日杯将棋オープン戦観戦記のページで観ることができます(2019年7月時点)。
先後逆のため、三間飛車側が1筋の端歩を突けており条件が良くなっている点はあるにせよ、参考1図から▲6五同歩以下左辺の攻防で三間飛車側がうまく立ち回って作戦勝ちとなりました。▲6六角打や▲6八銀引の構想はとても参考になります。
前述の将棋世界および付録発売の約2ヶ月後に本対局が行われていますが、付録の攻防と比較して本譜は先後ともに少し変化しています。より改良された攻防で三間飛車側が作戦勝ちになったとすると、▲6五同歩(△4五同歩)と取っても問題ないことになります。
しかし馬を作られたり飛車を取られて打ち込まれたりと激しい変化が多く、アマチュアが好んで選ぶべき変化とは言えなそうです。
△4三銀の変化
△4三銀の変化の場合、先手がなおも▲4四歩△同銀▲4五歩と攻めていくのは、△5五銀▲5六歩△同銀▲3三角成△同桂(第5図)となり、△3五角の王手飛車の筋があるため▲2四歩からの飛車先突破が成立せず、後手良しとなります。
後手の持駒:角 歩二 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂v銀v金 ・v金 ・ ・v香|一 | ・ ・ ・v王 ・ ・v飛 ・ ・|二 |v歩v歩v歩v歩v歩 ・v桂v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・ 歩 ・|五 | ・ ・ 歩 ・v銀 ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 ・ 歩 ・ ・ 歩 ・ 歩|七 | ・ ・ ・ 王 ・ 銀 ・ 飛 ・|八 | 香 桂 銀 金 ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:角 手数=0 △3三同桂まで
かといって先手が攻めあぐねるようだと△4二飛から△3二金とがっちり受け止められ、後手不満なしの展開でしょう。なお△4二飛・△3二金型の攻防については、最近では2019年5月に行われた第12期マイナビ女子オープン五番勝負第4局、▲里見香奈女流四冠 対 △西山朋佳女王戦が参考になります。

落ち着いた展開を好む方には、間違いなくこの△4三銀の変化の方がオススメです。
将棋世界2010年11月号
はじめに説明した通り、将棋世界2010年11月号の付録が「定跡次の一手 対後手三間飛車 いきなり早仕掛け」です。
amazonで古本を買う場合、付録が付いていないことがあるので、各出品者の出品情報をよく読んで注意しましょう。
他にも、例えばアマチュアの方の棋書になりますが、トマホークでおなじみのタップダイスさんの棋書「三間飛車VS超急戦」の第1章でも本戦法が解説されています。
▲4五歩対策は三間飛車党のさだめ
本記事では指し手の紹介はほとんどせず結論をあっさりと説明しましたが、実際にはこの「いきなり早仕掛け」は、一手受け間違えると簡単に攻めつぶされてしまう恐ろしい戦法です。
三間飛車に対しては▲4六歩〜▲4五歩と仕掛けておけばなんとなく手になってしまう、という恐ろしい一例でもあります。
三間飛車側が受け間違えてくれればそのまま優勢に、正しく受けられたらいったん攻めをあきらめて第2の駒組みへ、と考えると、居飛車のほうが気が楽と言えるかもしれません。
このいきなり早仕掛けをはじめ、居飛車の様々な形やタイミングでの▲4五歩に対応しなくてはならないのは三間飛車党のさだめです。
▲4五歩早仕掛けの亜種が多すぎて、一直線の定番定跡だけを丸暗記して対処できるものではないので、手筋集を読んで様々な手筋を覚え、形に応じて適材適所に活用するスタンスが良いのではないでしょうか。

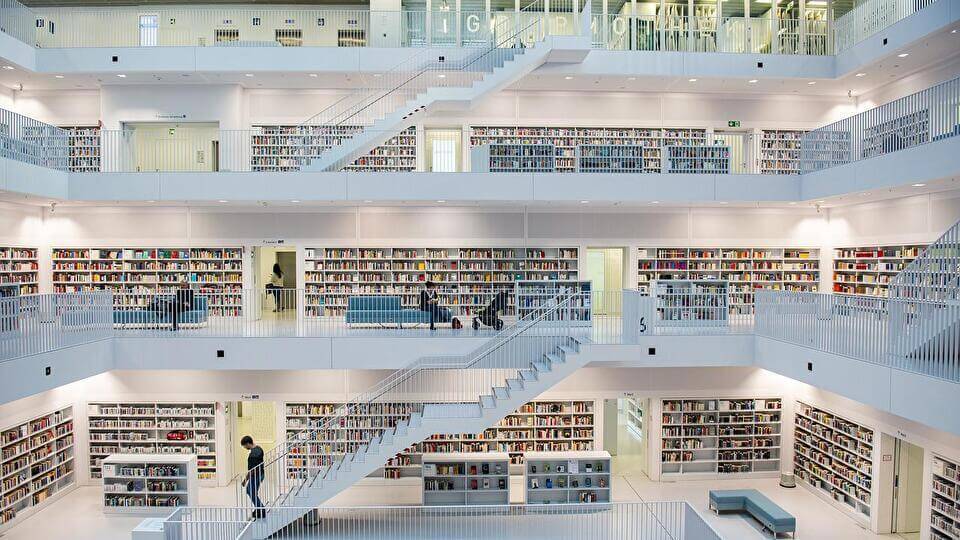
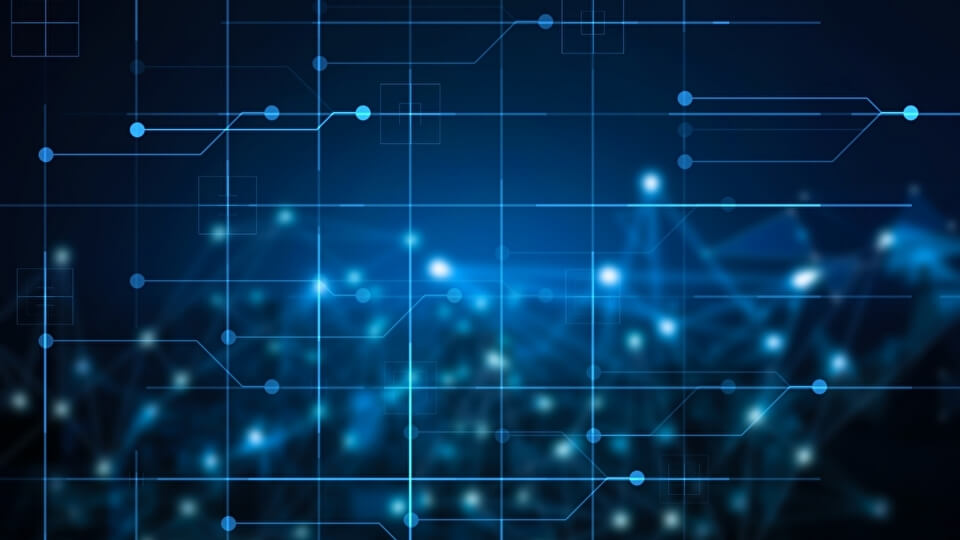
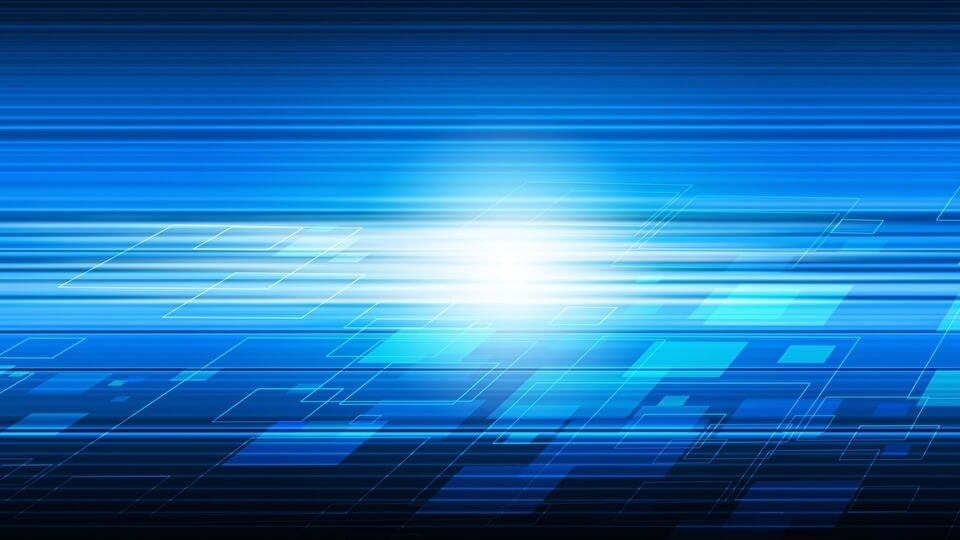
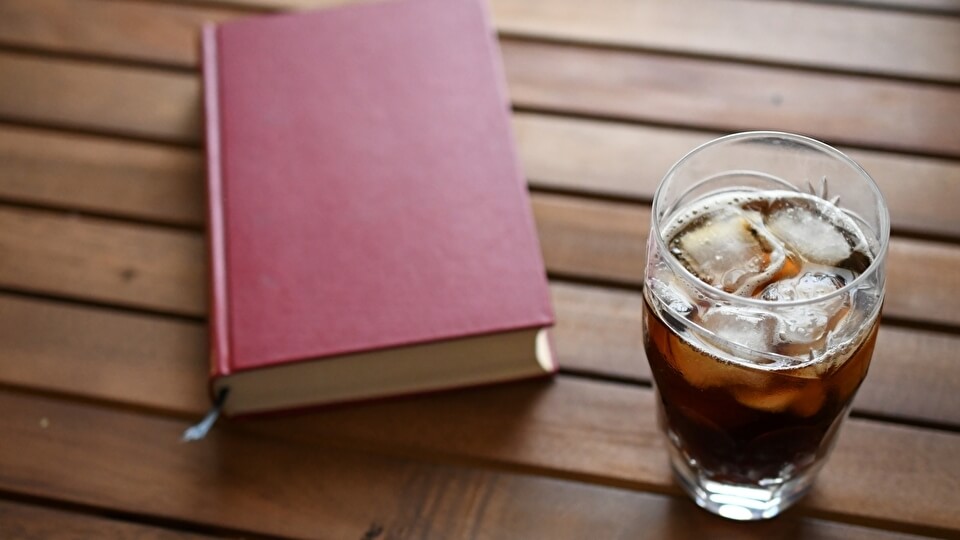








コメント