菅井ノート第4弾「相振り編」登場
「菅井ノート 相振り編」(菅井竜也王位 著)(Kindle版)を購入しました。ひとくちレビューをお送りします。
菅井ノート 後手編、先手編、そして実戦編に続く第4弾が、この相振り編です。
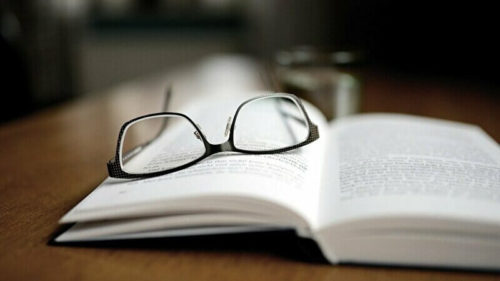
「本書を執筆し始めた頃は、まだ王位リーグを戦っている最中」(あとがきより)であり、その後王位のタイトル獲得当日に将棋情報局編集部による本書のリリースが発表され、そして2017年10月の発売と、忙しくかつノリに乗っている最中に執筆・発売されたのが本書です。
序章にて、「菅井流相振り飛車の極意」として述べられているのは、以下の方針です。
- B面攻撃
- 縦横無尽のさばき。相振り飛車ですが縦に戦うだけの将棋ではない
言われてみると、たしかに菅井流相振り飛車は総じてこの方針に沿っており、なるほどなと感じます。
第1章 向かい飛車 対 三間飛車
本書の表紙にもなっている、向かい飛車 対 三間飛車の菅井流(第1図。三間飛車側の布陣)。
後手の持駒:歩 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂v王v金 ・ ・ ・v桂v香|一 | ・ ・v銀 ・v金 ・ ・v角 ・|二 |v歩v歩v歩 ・v歩 ・ ・v歩v歩|三 | ・ ・ ・v歩v銀 ・v飛 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・ ・|五 | ・ 歩 歩 歩 銀 歩 ・ ・ ・|六 | 歩 ・ 角 ・ 歩 金 銀 歩 歩|七 | ・ 飛 ・ ・ ・ 王 金 ・ ・|八 | 香 桂 ・ ・ ・ ・ ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:歩 手数=0 △4五歩まで

この形が、「元祖」菅井流と言っていいでしょう。指し始めたのは菅井王位がまだ奨励会の級位者のときのこと。
驚くべきは、菅井王位がプロ棋士になってからの、公式戦における本戦術の採用数。これについては本書のコラム1を参照ください(全部で3つあるコラムも、初タイトル獲得となった王位戦の話題あり、すっかり定着した「菅井流」の話題ありで、面白いです)。
第1図は8筋が▲8六歩のケースですが、▲8五歩型、▲8七歩型の解説もあります。8筋に手数をかければかけるほど、矢倉囲い側にかける手数が減ります。この組み合わせごとに、後手の仕掛けがわずかに異なってくるのが将棋の奥深いところです。
この他に、▲5六銀保留型の解説もあります。
第2章 先手金無双 対 三間飛車
第2章は先手金無双 対 三間飛車(第2図)というタイトルですが、先手が美濃囲い(第3図)や▲3八金型とするケースもふんだんに解説されており、充実しています。
後手の持駒:歩 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂v王v金 ・ ・ ・v桂v香|一 | ・ ・v銀 ・v金v銀 ・v角 ・|二 |v歩v歩v歩v歩v歩v歩 ・v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・ ・ ・v飛 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ 歩 歩 ・ ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 角 銀 歩 歩 歩 歩 歩|七 | ・ 飛 ・ ・ 金 ・ 王 銀 ・|八 | 香 桂 ・ ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=0 △3八玉まで
後手の持駒:歩 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂v王v金 ・ ・ ・v桂v香|一 | ・ ・v銀 ・v金v銀 ・ ・ ・|二 |v歩v歩v歩v歩 ・v歩v角v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・v歩 ・v飛 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ 歩 歩 銀 歩 ・ ・ ・|六 | 歩 歩 角 ・ 歩 ・ 歩 歩 歩|七 | ・ 飛 ・ ・ 金 ・ 銀 ・ ・|八 | 香 桂 ・ ・ ・ 金 王 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=0 ▲4六歩まで
第3章 先手三間飛車 対 向かい飛車
第3章は先手三間飛車 対 向かい飛車。
3手目▲7五歩に対し、4手目△5四歩から向かい飛車に構える形(第4図)に対する先手の戦術を解説しています。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂v銀v金v王v金 ・v桂v香|一 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v飛 ・|二 |v歩v歩v歩v歩v銀v歩v角v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・v歩 ・v歩 ・ ・|四 | ・ ・ 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ ・ 歩 ・ ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 ・ ・ 歩 歩 歩 歩 歩|七 | ・ 角 飛 ・ ・ 王 銀 ・ ・|八 | 香 桂 銀 金 ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=4 △2二飛まで
最近は、4手目△5四歩から中飛車左穴熊を目指してくる相手が多い印象ですが、本書では取り上げられていません。後述の通り、菅井王位は、三間飛車に対する中飛車左穴熊は主導権を握りやすい作戦とは考えていないようです。
第4章 先手中飛車 対 三間飛車
第4章は、中飛車側を主観にして良くしにいく戦術の解説です。ですので、三間飛車側からしてみればあまり面白くない解説となります。
先手は中飛車左穴熊ではなく右側に玉を囲う、オーソドックスな相振り飛車です(第5図)。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂v銀v金v王 ・v銀v桂v香|一 | ・ ・ ・ ・v金 ・ ・v角 ・|二 |v歩v歩v歩v歩v歩v歩 ・v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・ ・ ・v飛 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ 歩 ・v歩 ・ ・|五 | ・ ・ 歩 ・ 飛 ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 ・ 歩 ・ 歩 歩 歩 歩|七 | ・ 角 ・ ・ ・ 王 ・ ・ ・|八 | 香 桂 銀 金 ・ 金 銀 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=0 ▲4八玉まで
中飛車左穴熊にした場合、
後手の石田流が非常に軽い形なので主導権を握られる可能性が高い
と菅井王位は述べています。
「得策ではない」と述べているわけではありませんが、「主導権を握って縦横無尽にさばいていく」という本書の方針には沿っていない、ということで見送ったのでしょう。
実践例を数多く紹介して、先手中飛車 対 後手三間飛車の相振り飛車の将棋を解説しています。
大きな特徴は、7筋の位をとりたくなるところを保留して▲7六歩型のままとする戦術を多くの取り上げているところでしょうか。メリットは、▲6六角と出ればすぐに角の効きが端に届くところ。また、保留した▲7五歩の一手を右辺に回せるのも利点です。
第5章 先手中飛車 対 向かい飛車
第5章では、満を辞して中飛車左穴熊の登場です。

こちらも第4章と同じく中飛車側を主観にしています。
第42回升田幸三賞受賞の一役を担った新構想、中飛車左穴熊 対 向かい飛車での有名な菅井流▲2八飛(第6図。飛車が5八から居飛車に逆戻り)がバッチリ解説されています。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂v銀v金v王v金v銀v桂v香|一 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v飛 ・|二 |v歩v歩v歩v歩v歩 ・v角 ・v歩|三 | ・ ・ ・ ・ ・v歩v歩 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ 歩 ・ ・v歩 ・|五 | ・ ・ 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 ・ 歩 銀 歩 歩 歩 歩|七 | ・ 角 ・ ・ ・ ・ ・ 飛 ・|八 | 香 桂 銀 金 王 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=0 ▲2八飛まで
まとめ
最後に「まとめチャート」と題して、各章の代表的な局面をチャート式に整理したものが載っており、わかりやすいです。
石田流または先手中飛車に対し、相手が相振り飛車を目指してきた場合の菅井流の戦術が、うまく整理されている、「菅井ノート 相振り編」。
主導権を握って積極的に戦いたい方におすすめです。

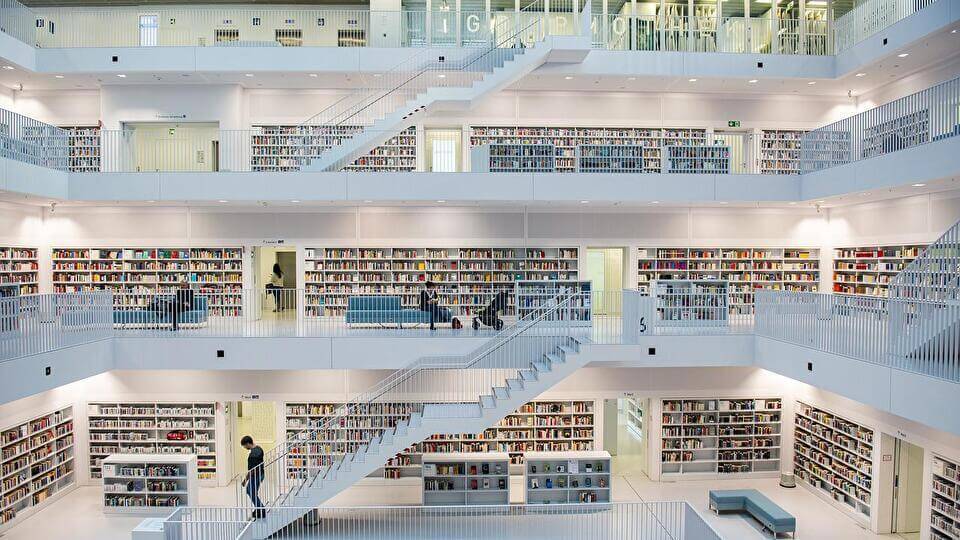
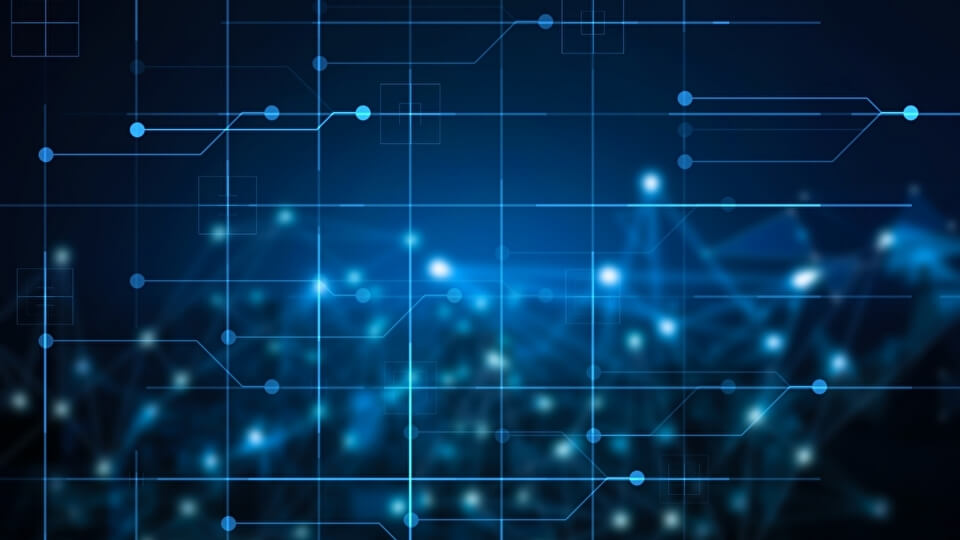
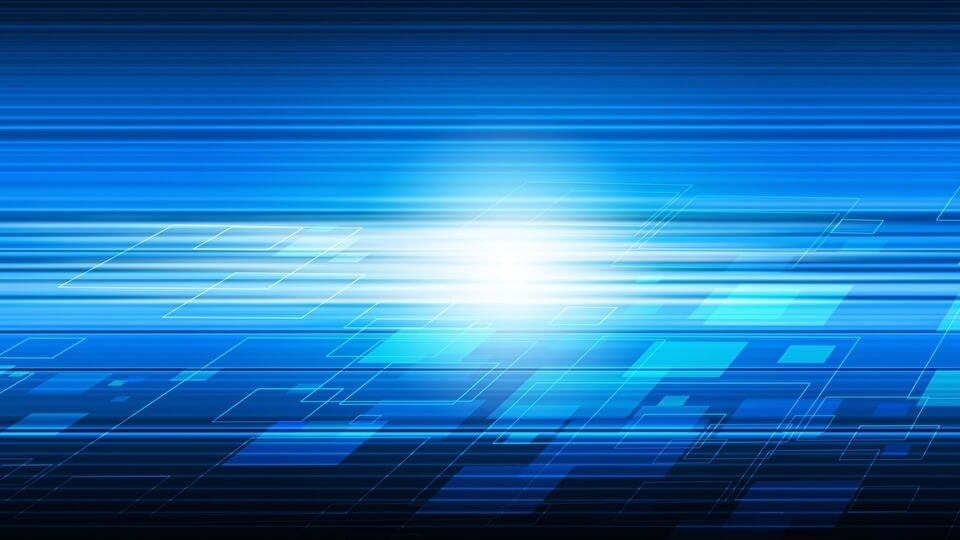
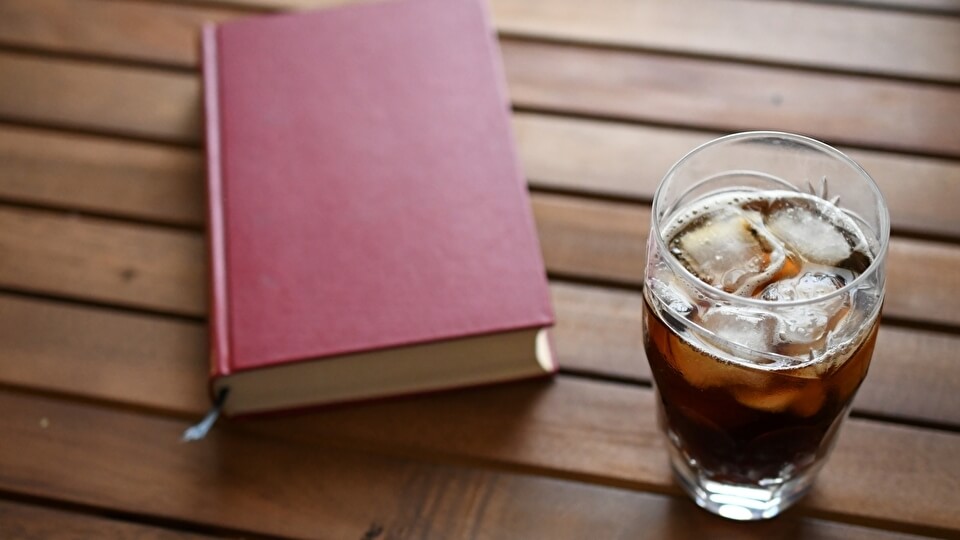





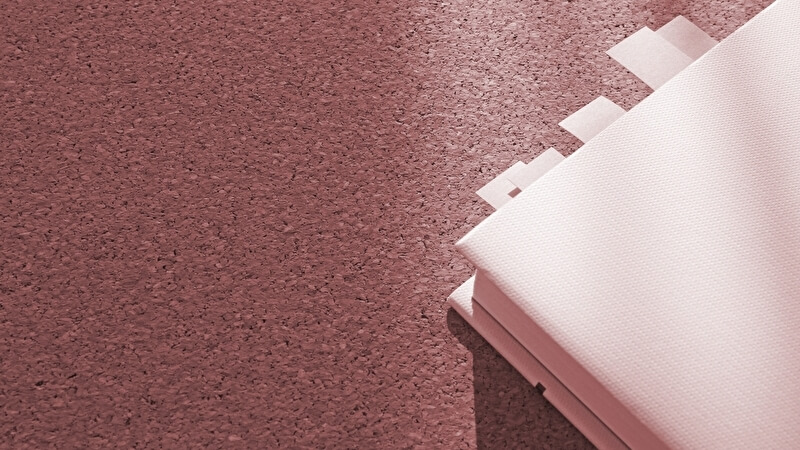

コメント