阪田流向かい飛車と菅井流三間飛車を徹底解説
「△3三金型振り飛車 徹底ガイド」のひとくちレビューをお送りします。
本書では、△3三金型振り飛車として阪田流向かい飛車(第1図)と菅井流三間飛車(第2図)の2つの戦法が徹底解説されています。
後手の持駒:角 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂v銀v金v王 ・v銀v桂v香|一 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v飛 ・|二 |v歩v歩v歩v歩v歩v歩v金v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・|五 | ・ ・ 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 ・ 歩 歩 歩 歩 ・ 歩|七 | ・ ・ ・ 王 ・ ・ ・ 飛 ・|八 | 香 桂 銀 金 ・ 金 銀 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:角 手数=10 △2二飛まで
後手の持駒:角 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂v銀v金v王 ・v銀v桂v香|一 | ・ ・ ・ ・ ・ ・v飛 ・ ・|二 |v歩v歩v歩v歩v歩v歩v金v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・|五 | ・ ・ 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 ・ 歩 歩 歩 歩 ・ 歩|七 | ・ ・ ・ 王 ・ ・ ・ 飛 ・|八 | 香 桂 銀 金 ・ 金 銀 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:角 手数=10 △3二飛まで

これらの戦法を専門的に解説する棋書はほとんどなく、とりわけ菅井流三間飛車を解説する棋書は2020年11月時点で他には皆無のため、とても貴重です。
著者は安用寺孝功六段。現在順位戦C級1組に在籍するベテラン振り飛車党です。
安用寺六段は本書のほかに「1冊で全てわかる向かい飛車 その狙いと対策」と「角交換四間飛車戦記 2008~2019」をリリースしています。

菅井竜也八段が菅井流三間飛車の章を執筆・解説してくれていたらなおさらよかったですが、あたためている研究を披露するわけにもいかなかったのでしょう。
前者の「角交換振り飛車編」では、自戦解説の形で菅井八段による菅井流三間飛車の解説を堪能できることでしょう。
本書の目次
目次は以下の通りです。
序章 △3三金型振り飛車の基本
第1章 阪田流向かい飛車 △5二金型速攻
第2章 阪田流向かい飛車 △7二玉型
第1節 ▲7七銀型
第2節 ▲7七銀保留型
第3章 阪田流向かい飛車 対左美濃
第4章 阪田流向かい飛車 持久戦編
第5章 △3三金型三間飛車
第1節 △3三桂~△2五桂型
第2節 △5四銀型
第3節 ▲5六歩型
阪田流向かい飛車が第1章から第4章までの約150ページを占める一方、菅井流三間飛車(△3三金型三間飛車)は第5章のみで70ページ弱の分量です。
これは菅井流がまだ誕生したばかりで実戦数が少なく、定跡が確立していないためと考えられます。
以下、菅井流三間飛車にしぼってレビューします。
△5四歩型と△4四歩型
第5章の△3三金型三間飛車は、「第1節 △3三桂~△2五桂型」、「第2節 △5四銀型」、「第3節 ▲5六歩型」の3節で構成されています。
「第1節 △3三桂~△2五桂型」では、△5四歩型が解説されています(参考1図)。
後手の持駒:角 歩 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・ ・ ・ ・v香|一 | ・v王v銀 ・ ・v銀v飛 ・ ・|二 | ・v歩v歩v歩 ・v歩 ・ ・v歩|三 |v歩 ・ ・ ・v歩 ・v金v歩 ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩v桂 ・|五 | 歩 ・ 歩 歩 ・ 歩 ・ 飛 ・|六 | ・ 歩 銀 ・ 歩 銀 歩 ・ 歩|七 | ・ 王 金 ・ 金 ・ ・ ・ ・|八 | 香 桂 ・ ・ ・ ・ ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:角 手数=0 △5四歩まで
△5四歩型は、2017年8月に行われた第58期王位戦第5局、▲羽生善治三冠 対 △菅井竜也七段戦(肩書・段位は当時)にて菅井七段が披露した形であることから、本筋の展開といえるでしょう。

「角交換に5筋を突くな」の格言が当てはまらないのは、升田式石田流と同様です。
一方で、「第2節 △5四銀型」では△4四歩型が解説されています(参考2図。このあと△4三銀~△5四銀と上がっていくような展開)。
後手の持駒:角 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・ ・ ・v桂v香|一 | ・v王v銀 ・ ・v銀v飛 ・ ・|二 | ・v歩v歩v歩v歩 ・ ・v歩v歩|三 |v歩 ・ ・ ・ ・v歩v金 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩 歩 ・|五 | 歩 ・ 歩 ・ ・ 歩 ・ ・ ・|六 | ・ 歩 銀 歩 歩 銀 歩 ・ 歩|七 | ・ 王 ・ ・ 金 ・ ・ 飛 ・|八 | 香 桂 ・ 金 ・ ・ ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:角 手数=0 △4四歩まで
こちらも第1節と同様△3三桂~△2五桂で一歩得するのが基本的な狙いとなります。
▲5六歩型も手強い相手
参考1図、参考2図の通り、居飛車は▲4六歩・▲4七銀型で対抗するのが一般的といえますが、▲5六歩型(参考3図)も十分手強い相手であり、その変化を解説しているのが「第3節 ▲5六歩型」です。
後手の持駒:角 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂v銀v金 ・ ・v銀v桂v香|一 | ・ ・v王 ・ ・ ・v飛 ・ ・|二 |v歩v歩v歩v歩v歩v歩v金v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・|五 | ・ ・ 歩 ・ 歩 ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 ・ 歩 ・ 歩 歩 ・ 歩|七 | ・ ・ 王 ・ ・ 銀 ・ 飛 ・|八 | 香 桂 銀 金 ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:角 手数=0 ▲5六歩まで
ハマらずに、打開できるようになるために
菅井流三間飛車(△3三金型三間飛車)は、駒組みの手順を間違えるとあっという間に不利になる落とし穴が多数あります。
相手にとっては見慣れない、自分の土俵で戦うことができる戦法ですが、自らもハマる落とし穴だらけの土俵であることは自覚しなくてはなりません。
また、△3四金+△3三桂(△2五桂)の凝り形のほぐし方、さばき方にはコツが要ります。
この「△3三金型振り飛車 徹底ガイド」を読むことで、落とし穴を知り、打開手段を学ぶことができます。
居飛車の駒組みの自由度は高く、本書と全くの同一局面が現れることはまれでしょう。指す前に本書を繰り返し読む、または実戦で試してみて痛い目に会ったときに本書を読み返すことで、局面に応じて頭の引き出しの中から適切な打開策をピックアップして指していけるようになるのではないでしょうか。
関連記事
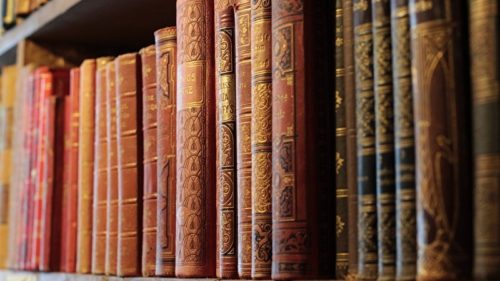

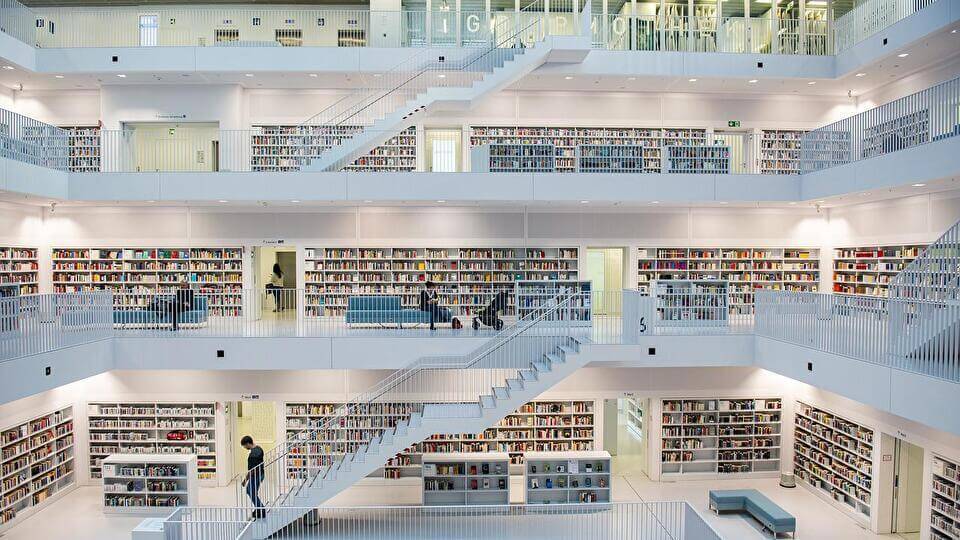
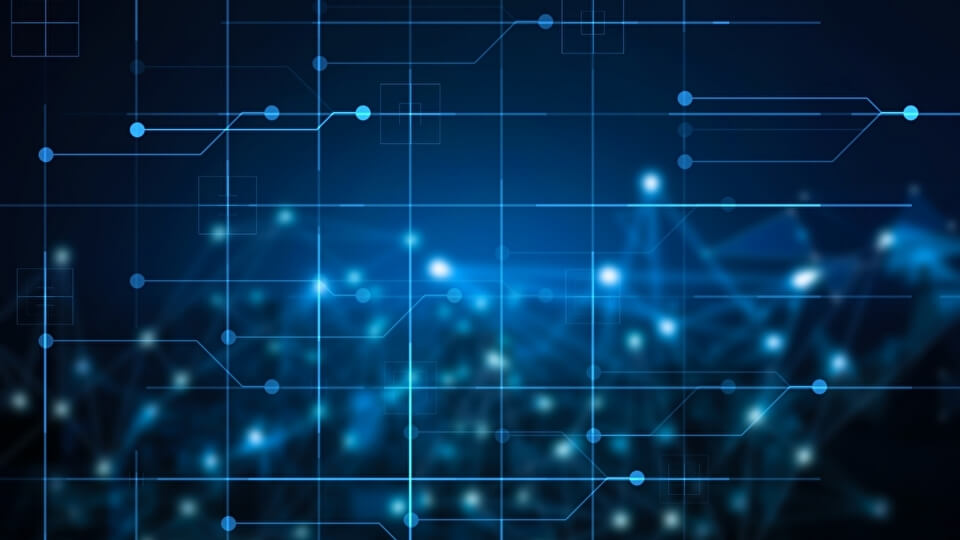
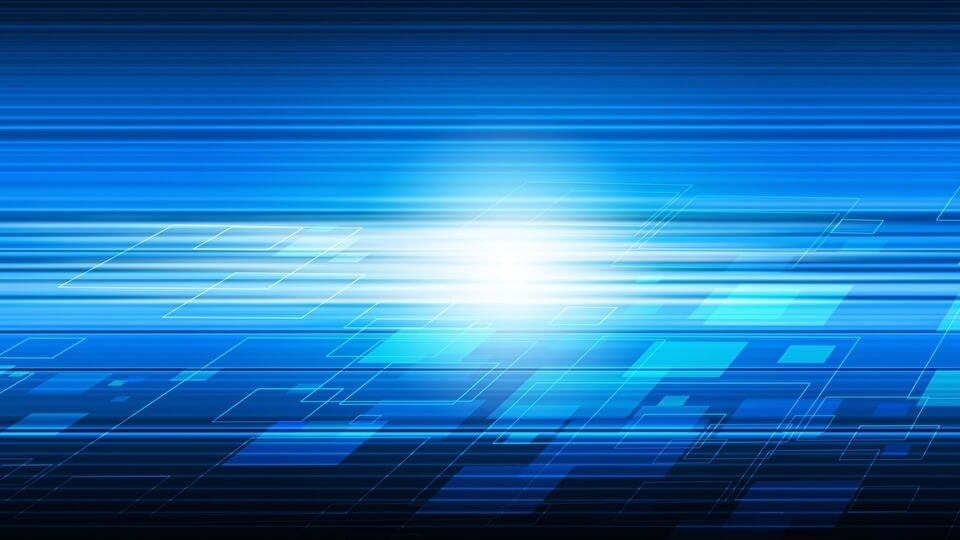
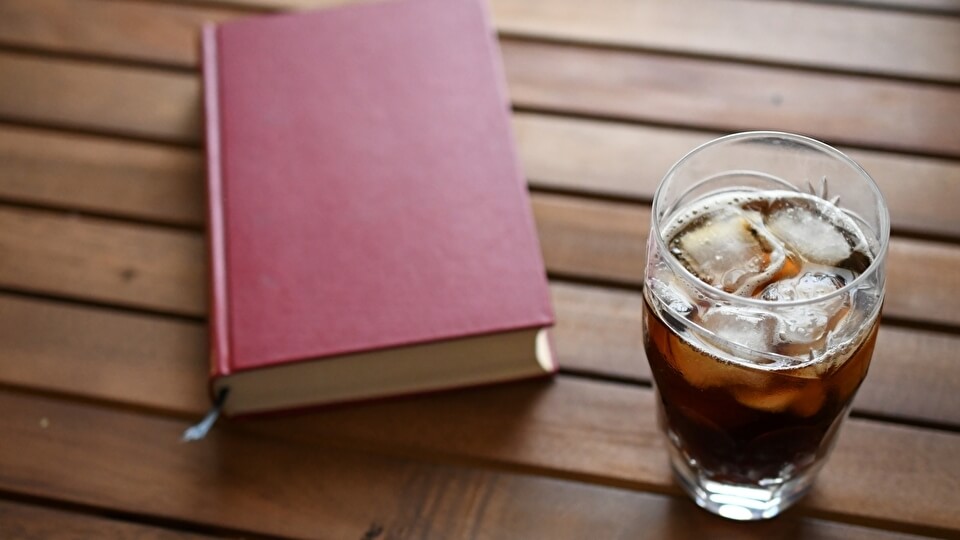







コメント