石田流党にもオススメの石田流対策本
「石田流破り 左美濃徹底ガイド」のひとくちレビューをお送りします。
まず、なぜ石田流対策本なのにレビューしているのかというと、石田流側の立場から読んでも非常に参考になる、内容充実の一冊だからです。石田流のいろいろな仕掛けや、うまく行くケース/行かないケースなどのノウハウを学ぶことができます。
著者は八代弥七段。2016年の第10回朝日杯将棋オープン戦で優勝した若手実力者です(ちなみに第11回と第12回の優勝者は藤井聡太七段)。
本書を読んでいると、八代七段が2010年代前半当時の石田流VS左美濃の最新定跡を惜しげなく懇切丁寧に解説している感が伝わってきて、好感が持てます。
タイトル通り居飛車寄りの棋書であるにも関わらず、「ココセ」がないので章・節の結論が互角だったりもします。
対石田流本組み、石田流▲7七角型、右銀保留型も
本書の目次は以下の通りです。
第1章 対石田流本組み
第1節 対石田流本組み基本形
第2節 飛車先保留型
第2章 対石田流▲7七角型
第3章 対▲3九玉型
第4章 居飛車右銀保留型
以下、石田流目線でレビューします。
対石田流本組み
第1章は対石田流本組み。角を9七に構える、正調石田流VS左美濃の戦いです(第1図)。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・ ・ ・ ・ ・v桂v香|一 | ・v飛 ・ ・v金 ・v金v王 ・|二 | ・ ・v歩v銀v歩v歩v角v銀 ・|三 |v歩 ・ ・v歩 ・ ・v歩v歩v歩|四 | ・v歩 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | 歩 ・ 飛 歩 銀 ・ ・ ・ 歩|六 | 角 歩 桂 ・ 歩 歩 歩 歩 ・|七 | ・ ・ ・ ・ 金 ・ 銀 王 ・|八 | 香 ・ ・ ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=0 △9四歩まで

一般に、左美濃に対して石田流本組みだと苦しいので▲7七角型が広まった背景がありますが、石田流本組みでも意外と戦えることがわかります。
本書で解説されている定跡を理解しておけば、アマチュア初段レベルならば完全に互角かそれ以上でしょう。
第1章・第2節では、居飛車の飛車先の歩が8五ではなく8四にいる飛車先保留型を解説しています。飛車先を保留することで、△8五歩型とは全く異なる戦術が生まれるのが将棋の奥深く面白いところです。
対石田流▲7七角型
第2章は対石田流▲7七角型(第2図)。角交換から始まるさばきを重視した石田流です。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・ ・ ・v金 ・v桂v香|一 | ・v飛 ・ ・v金 ・v銀v王 ・|二 |v歩 ・v歩v銀v歩v歩v角 ・ ・|三 | ・ ・ ・v歩 ・ ・v歩v歩v歩|四 | ・v歩 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ 飛 歩 ・ ・ ・ ・ 歩|六 | 歩 歩 角 銀 歩 歩 歩 歩 ・|七 | ・ ・ ・ ・ 金 ・ 銀 王 ・|八 | 香 桂 ・ ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=0 △8五歩まで
2010年代現在は対左美濃ではこの▲7七角型のほうが主流であり、また変化が複雑であることから、本章に最も多くのページ数を割いています。そのページ数はなんと80ページ!ものすごい充実ぶりです。
対▲3九玉型
第3章は対▲3九玉型(第3図)。飛車・角の動きよりも、玉頭攻めを優先した布陣です。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・ ・ ・v金 ・v桂v香|一 | ・v飛 ・ ・v金 ・v銀v王 ・|二 |v歩 ・v歩v銀v歩v歩v角v歩 ・|三 | ・v歩 ・v歩 ・ ・v歩 ・v歩|四 | ・ ・ 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ ・ 歩 銀 歩 ・ ・ 歩|六 | 歩 歩 ・ ・ 歩 ・ 歩 歩 ・|七 | ・ 角 飛 ・ 金 ・ 銀 ・ ・|八 | 香 桂 ・ ・ ・ 金 王 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=0 ▲5六銀まで
第3図以下、▲3六歩〜▲3七桂〜▲2六歩〜▲2五歩のように攻めていきます。
本書が発売されたのは2014年2月。2014年11月に登場した、▲4六歩と▲3六歩を突かず▲3九玉型+端桂(▲1七桂)からさらに速い玉頭攻めを仕掛ける「宮本流」は当然載っていません。

しかし▲1七桂と跳ねる宮本流は、後戻りできず乱戦含みでまとめるのが難しい、プロ好みの超攻撃的戦術です。アマチュアには本章で解説されている▲3九玉型+▲3七桂の方がわかりやすいでしょう。
居飛車右銀保留型
最後の第4章は居飛車右銀保留型。居飛車側が5筋と6筋の歩を突かず、玉の囲いを急ぐ戦術です(第4図)。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・v金v王v桂v香|一 | ・ ・ ・v銀 ・ ・v銀v角 ・|二 |v歩 ・v歩v歩v歩v歩 ・v歩v歩|三 | ・v飛 ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・|四 | ・v歩 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ 飛 歩 ・ ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 ・ ・ 歩 歩 歩 歩 歩|七 | ・ 角 ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・|八 | 香 桂 銀 金 ・ 金 王 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=0 △8四飛まで
ノーマル三間飛車VS5筋不突き居飛車穴熊の戦型は、トマホークの登場により非常に有名になりました。

が、この先手石田流VS5筋・6筋不突き左美濃は珍しい戦型と言えます。
第4図から、石田流側が速攻を仕掛ければ第3章までとはまた一風変わった面白い戦いとなります。じっくり戦う場合は、居飛車側の方針次第で第3章までの形に合流することもあれば、双方一直線に固め合う展開になることもあります。
相対することはまれでしょうが、この見慣れない居飛車右銀保留型に対しどう戦うべきなのかきちんと知っておきたい石田流党の方は、本書を読んでみると良いでしょう。
現在でも通用する石田流VS左美濃の戦術書
最近のプロ棋界では、先手石田流で苦しいととらえられている変化があるからか(下記記事で紹介されているエルモ囲い右四間や4手目△1四歩などが考えられます)、または(かつ)そもそも2手目△8四歩と突く居飛車党が増えている(これだと先手石田流にできない)からか、先手石田流の実戦例が減っています。
そのため定跡の進歩も緩やかで、良い方向に考えると、2014年に発売された本書はとりわけアマチュア棋界では現在でも十分通用する内容と言えると思います(宮本流は載っていませんが、しっかり囲って戦いたい方には問題ないでしょう)。
居飛車党にとっても石田流党にとってもためになる、充実の一冊です。

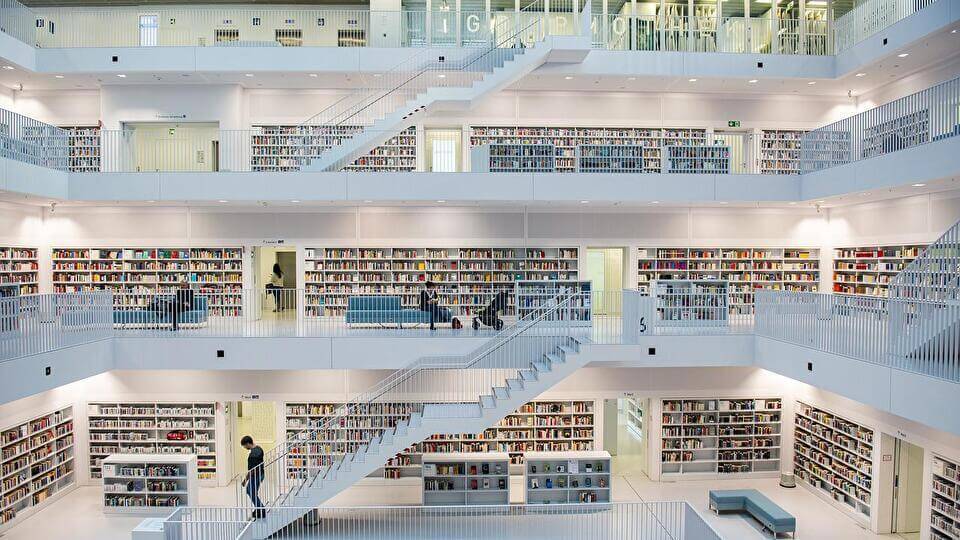
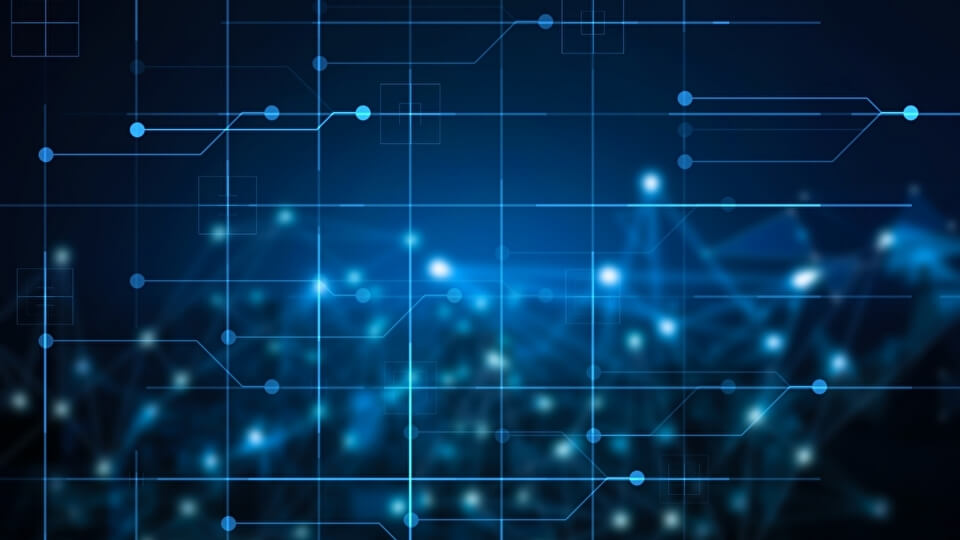
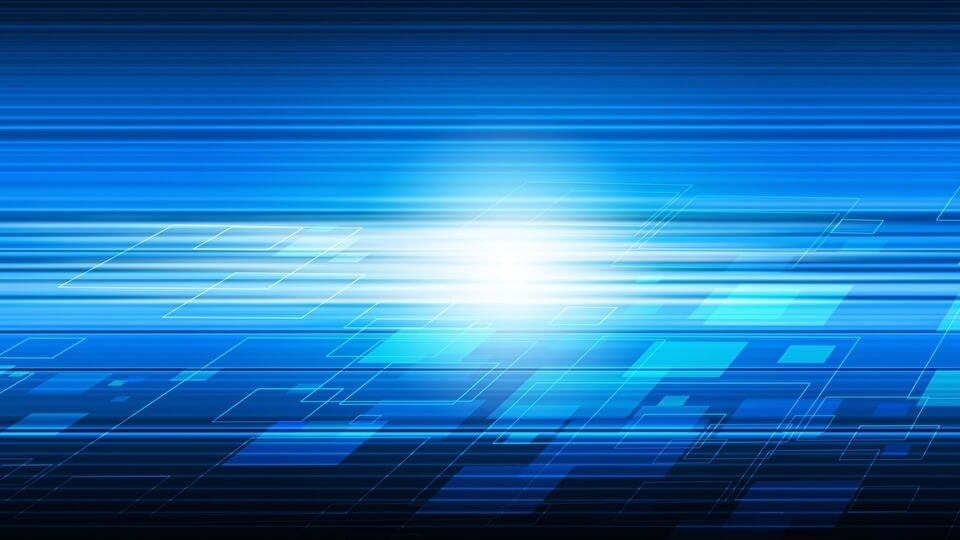
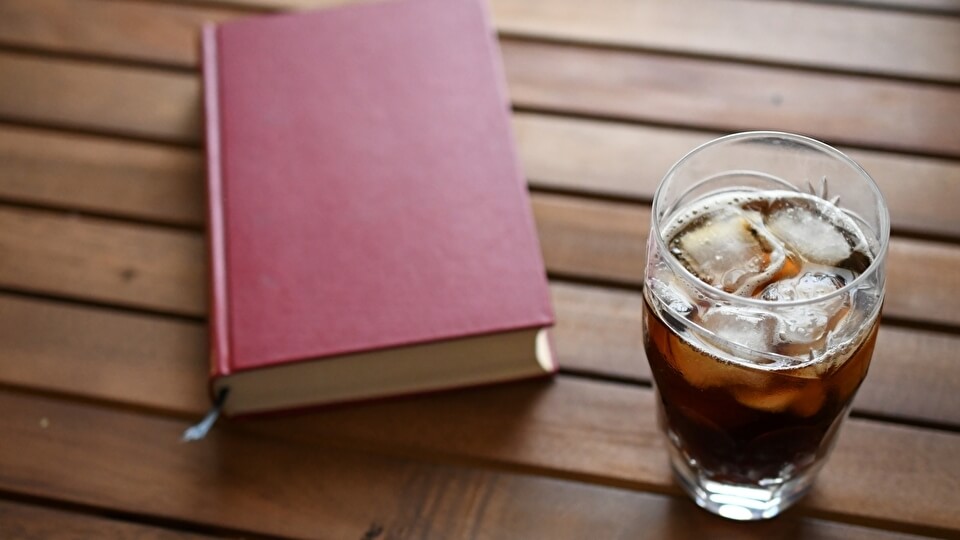










コメント