角交換型の石田流
「升田式石田流」とは、その名の通り升田幸三実力制第4代名人が編み出した石田流の布陣です(第1図)。
後手の持駒:角 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・v金v銀v桂v香|一 | ・v飛 ・ ・ ・ ・v王 ・ ・|二 |v歩 ・v歩v銀v歩v歩 ・v歩v歩|三 | ・ ・ ・v歩 ・ ・v歩 ・ ・|四 | ・v歩 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ 飛 ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 ・ 歩 歩 歩 歩 歩 歩|七 | ・ 銀 金 ・ ・ ・ 銀 王 ・|八 | 香 桂 ・ ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:角 手数=19 ▲7八金まで
升田式石田流の駒組みの特徴として、下記が挙げられます。(石田流側を先手としています)
- 角交換型
- ▲6六歩はできるだけ保留
- ▲7八金型
一番の特徴は、「角交換型」という点でしょう。角交換がないと升田式石田流ではない、と言っても過言ではありません。
居飛車側からの角交換を誘うため、▲6六歩はできるだけ保留します。ちなみに自分から角交換をすると一手損になってしまうので、あまりおすすめできません。
もし居飛車側が角交換をしてこなければ、▲7六飛のあと角道を止めて「石田流本組み」にスイッチすることもできます。

続いて、角交換をして浮き飛車にすると、必然的に左辺下部が薄くなり角打ちに非常に弱くなるため、バランス重視で▲7八金型をとることになります。
升田式石田流の組み方
升田式石田流の組み方の参考手順は以下の通りです。
初手からの指し手
▲7六歩 △3四歩
▲7五歩 △8四歩
▲7八飛 △8五歩
▲4八玉 △6二銀
▲3八玉 △4二玉
▲7六飛 (第2図)
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・v金v銀v桂v香|一 | ・v飛 ・v銀 ・v王 ・v角 ・|二 |v歩 ・v歩v歩v歩v歩 ・v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・|四 | ・v歩 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ 飛 ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 ・ 歩 歩 歩 歩 歩 歩|七 | ・ 角 ・ ・ ・ ・ 王 ・ ・|八 | 香 桂 銀 金 ・ 金 銀 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=11 ▲7六飛まで
手順中△6二銀に対し▲7四歩と突く手が見えます。これが「早石田」という奇襲戦法です。

奇襲戦法の書籍だと、ここで△7四同歩と取ってくれるので先手も十分に戦えますが、 実際には手厚く△7二金!(失敗図)で受け止められてしまいますので注意。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・ ・v王v金v銀v桂v香|一 | ・v飛v金v銀 ・ ・ ・v角 ・|二 |v歩 ・v歩v歩v歩v歩 ・v歩v歩|三 | ・ ・ 歩 ・ ・ ・v歩 ・ ・|四 | ・v歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 ・ 歩 歩 歩 歩 歩 歩|七 | ・ 角 飛 ・ ・ 王 ・ ・ ・|八 | 香 桂 銀 金 ・ 金 銀 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=10 △7二金まで
「新・石田流(7手目▲7四歩)」の変化と違い、金銀2枚で7三の地点が守られているため、攻め切れません。

そのため、▲7四歩とはせず▲3八玉と寄ります。
浮き飛車にしたあと
第2図以下の指し手
△8八角成
▲同 銀 △6四歩
▲2八玉 △6三銀
▲3八銀 △3二玉
▲7八金 (再掲載第1図)
後手の持駒:角 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・v金v銀v桂v香|一 | ・v飛 ・ ・ ・ ・v王 ・ ・|二 |v歩 ・v歩v銀v歩v歩 ・v歩v歩|三 | ・ ・ ・v歩 ・ ・v歩 ・ ・|四 | ・v歩 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ 飛 ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 ・ 歩 歩 歩 歩 歩 歩|七 | ・ 銀 金 ・ ・ ・ 銀 王 ・|八 | 香 桂 ・ ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:角 手数=19 ▲7八金まで
第1図がオーソドックスな一例です。
はじめに解説した通り、△8八角成のところで角交換を保留してくるならば、▲6六歩から石田流本組みを目指すこともできます。
▲7八金以下の駒組み
第1図以下、先手は①▲7七銀型(第3図)か、②▲7七桂+▲5七銀型か、または③▲7七桂+▲6七銀型とするのが一般的です。
後手の持駒:角 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・v金 ・v桂v香|一 | ・v飛 ・ ・ ・v銀v王 ・ ・|二 |v歩 ・v歩v銀v歩v歩 ・v歩 ・|三 | ・ ・ ・v歩 ・ ・v歩 ・v歩|四 | ・v歩 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ 飛 ・ ・ ・ ・ ・ 歩|六 | 歩 歩 銀 歩 歩 歩 歩 歩 ・|七 | ・ ・ 金 ・ ・ ・ 銀 王 ・|八 | 香 桂 ・ ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:角 手数=23 ▲7七銀まで
①▲7七銀型は、8筋から逆襲を狙っていく積極的な手。▲6六銀〜▲5五銀や▲6六銀〜▲5六歩〜▲5五歩から中央志向で戦うこともできます。2017年時点で最有力とされています。
②▲7七桂+▲5七銀型、③▲7七桂+▲6七銀型は手詰まりになりやすいと言われていますが、バランスの取れた美しい布陣にできますし、じっくりとした戦いが好きな方にお勧めです。
▲7七桂型の場合、左銀は8八〜7九〜6八のルートで中央に移動させます。
後手番の場合
後手番では、1手の違いにより一直線に石田流や升田式石田流を目指すのは難しいとされています。
そこで、△3二飛と直接振らずに△4二飛と途中下車したあと△3二飛と振り直す戦術が発明されました。それが「3・4・3戦法」と「4→3戦法」です。これらについては以下の記事を参照ください。


ノーマル三間飛車に慣れた方にオススメ
角交換型の石田流のため、角の打ち込みのスキに気を使う展開になりがちな升田式石田流。ノーマル三間飛車に慣れた後に採用することをオススメします。
関連棋書
「これだけで勝てる 石田流のコツ」の第3章「対急戦編」で、升田式石田流の戦い方が詳しく解説されています。
関連記事


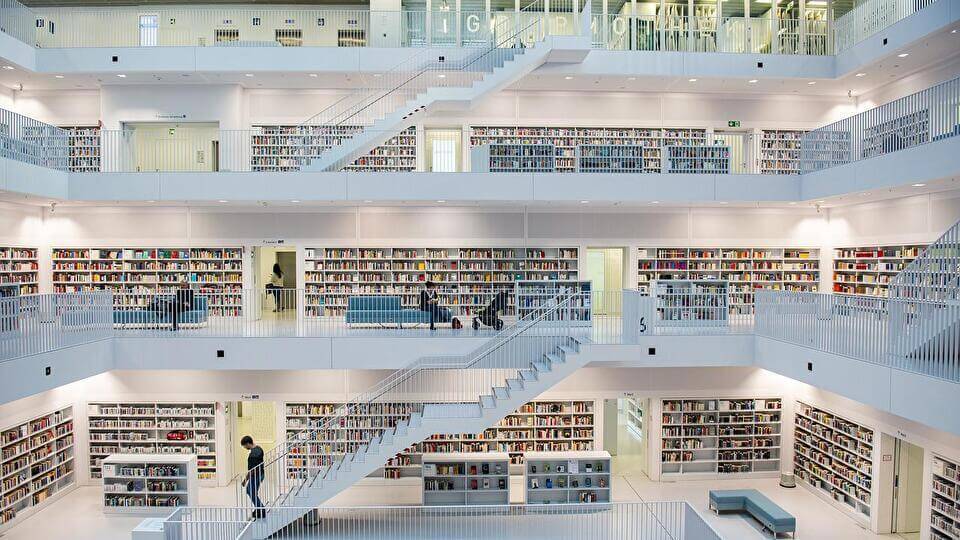
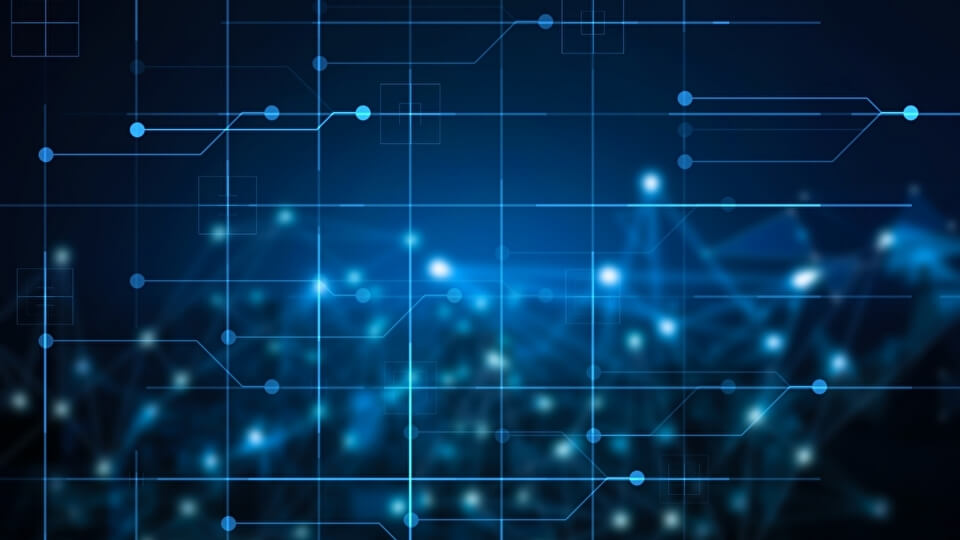
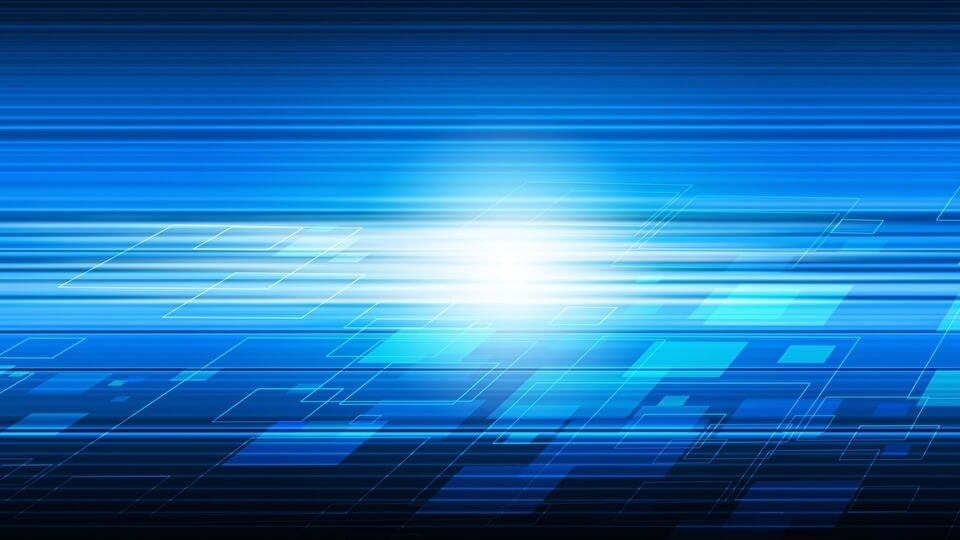
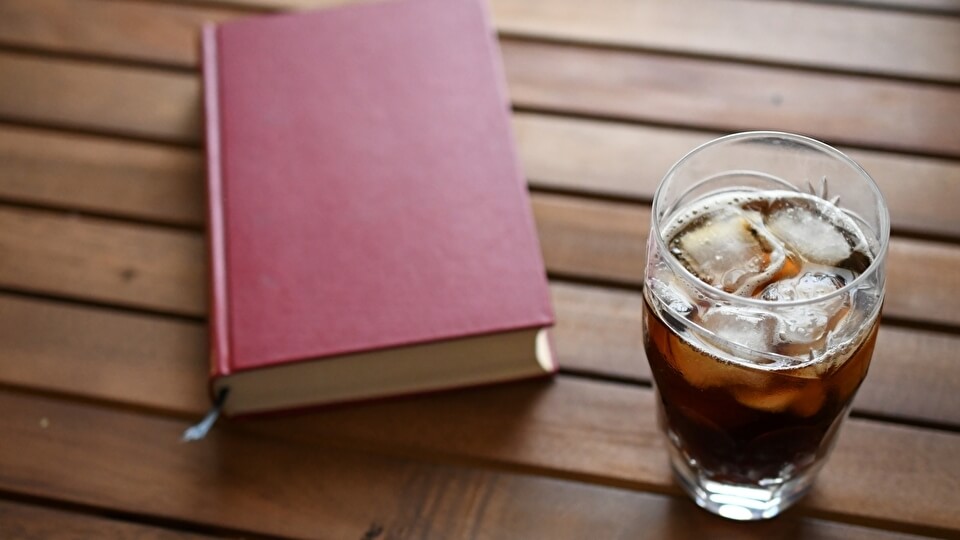






コメント