目次
振り飛車穴熊 VS 居飛車穴熊
居飛車穴熊に堅さ負けしたくない、という人にとってうってつけでしょう。振り飛車側も同じく穴熊に組んでしまいます。
振り飛車側の穴熊なので、「振り飛車穴熊」と呼びます。三間飛車との組み合わせの場合、「三間飛車穴熊」と呼んでもかまいません。
そして、両者穴熊の戦型を「相穴熊」と呼びます(第1図)。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・ ・ ・ ・v金v桂v王|一 | ・v飛 ・ ・ ・ ・v金v銀v香|二 |v歩 ・v歩v歩 ・v歩v角v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・v歩v銀v歩 ・ ・|四 | ・v歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ 歩 歩 歩 銀 歩 ・ ・|六 | 歩 歩 角 ・ ・ 歩 ・ 歩 歩|七 | ・ ・ 飛 ・ ・ ・ ・ 銀 香|八 | 香 桂 ・ ・ ・ 金 金 桂 王|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=36 △4四銀まで
振り飛車穴熊を目指すのであれば、まずは左辺にはあまり手をかけずに、さっさと玉を1九に潜り▲2八銀とハッチを閉めることを優先した方が良いでしょう。
穴熊囲いが不十分なまま居飛車に戦いを起こされると、収拾がつかなくなる恐れがあります。
銀冠穴熊に発展することも
戦いを起こす主導権は基本的に居飛車側にあり、居飛車側がしかけを保留し続ける場合、第2図のようにおたがいさらに囲いに手をかけ、▲2七銀型(△2三銀型)穴熊に発展することもあります。なお、この形を「銀冠穴熊」と呼びます。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・ ・ ・ ・ ・v桂v王|一 | ・v飛 ・ ・ ・ ・v金v金v香|二 |v歩 ・v歩v歩 ・v歩v角v銀 ・|三 | ・ ・ ・ ・v歩v銀v歩v歩v歩|四 | ・v歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ 歩 歩 歩 銀 歩 歩 歩|六 | 歩 歩 角 ・ ・ 歩 ・ 銀 ・|七 | ・ ・ 飛 ・ ・ ・ 金 金 香|八 | 香 桂 ・ ・ ・ ・ ・ 桂 王|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=45 ▲2八金上まで
石田流との組み合わせは上級者向け
振り飛車側の左辺は石田流に組むこともできます(参考1図)。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・ ・ ・ ・v金v桂v王|一 | ・ ・ ・ ・ ・v金 ・v銀v香|二 | ・ ・v歩v歩v銀v歩v角v歩v歩|三 |v歩v飛 ・ ・v歩 ・v歩 ・ ・|四 | ・v歩 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | 歩 ・ 飛 歩 ・ ・ ・ ・ ・|六 | 角 歩 桂 銀 歩 歩 歩 歩 歩|七 | ・ ・ ・ ・ ・ 金 ・ 銀 香|八 | 香 ・ ・ ・ ・ ・ 金 桂 王|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=37 ▲4八金左まで
あわせて読みたい


石田流の基礎知識 石田流本組みとは
「石田流本組み」とは、角交換しない▲9七角・▲7七桂型石田流です。攻守に優れた美しい布陣です。早い段階で▲6六歩と突いて角交換が起こらないようにしてから、▲7六飛で8筋を受け、その後▲9七角、▲7七桂と上がります。
が、当然石田流は組み上げるまでに手数がかかるため、穴熊囲いがおろそかになる危険性があります。また、石田流は左辺に駒が片寄るうえ、縦に伸びた軽い形。右辺に駒が片寄る振り飛車穴熊と組み合わせると中央が手薄になります。
そのため「石田流+穴熊」は指しこなすのが難しいといえます。
参考棋書
三間飛車穴熊VS居飛車穴熊の参考書籍はあまりない気がします。以下の書籍くらいでしょうか。
このうち 「中飛車道場〈第4巻〉6四銀・ツノ銀」は、タイトルの通り厳密には中飛車穴熊VS居飛車穴熊が紹介されているのですが、三間飛車穴熊からも同様の形に持ち込める変化が紹介されているため、三間穴熊党にとっても参考になります。

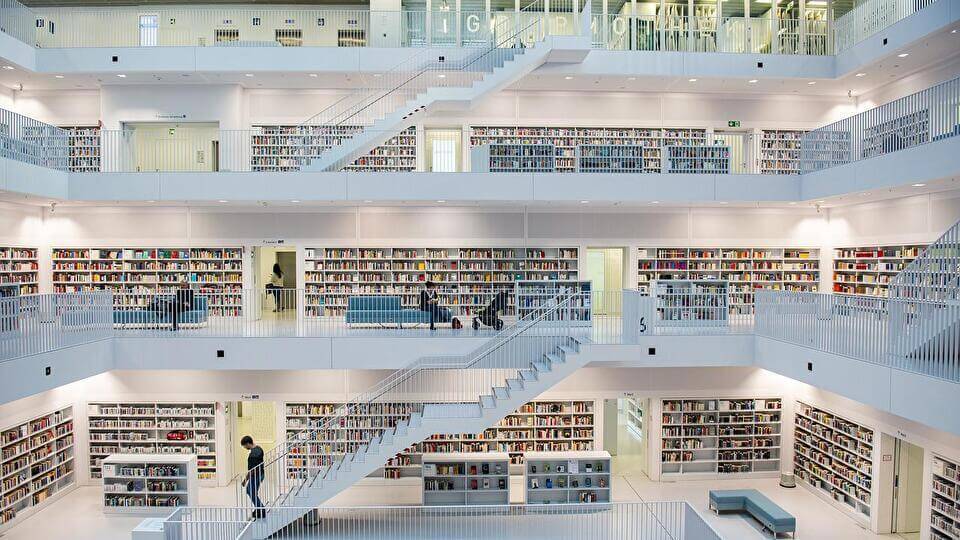
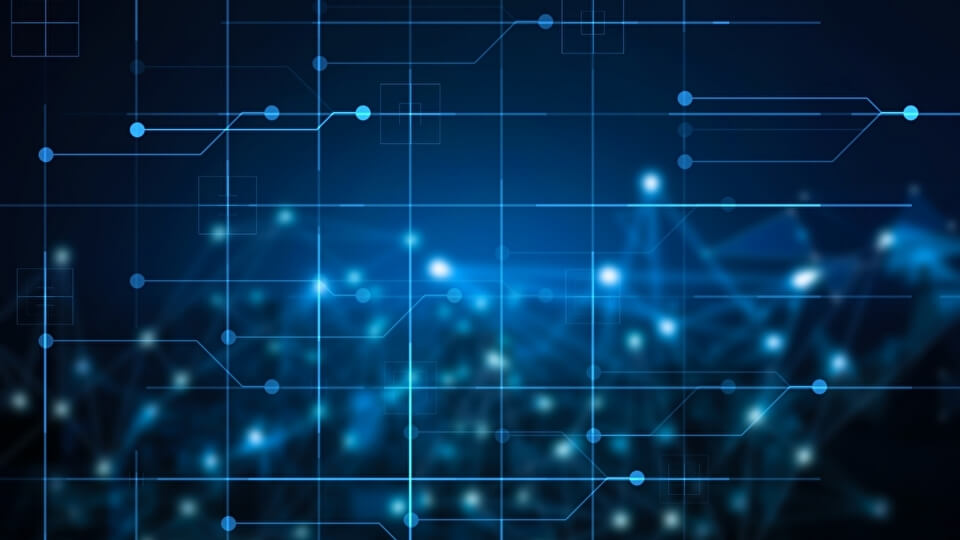
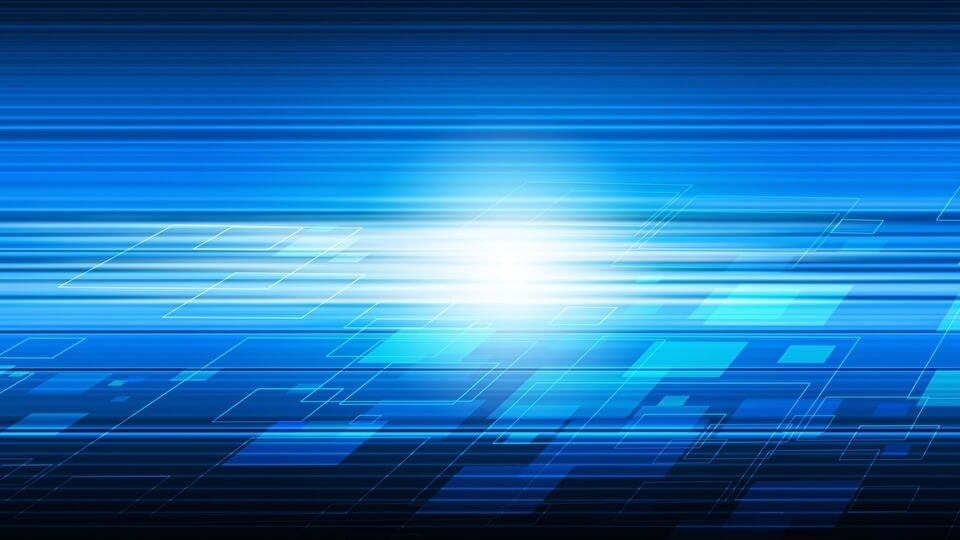
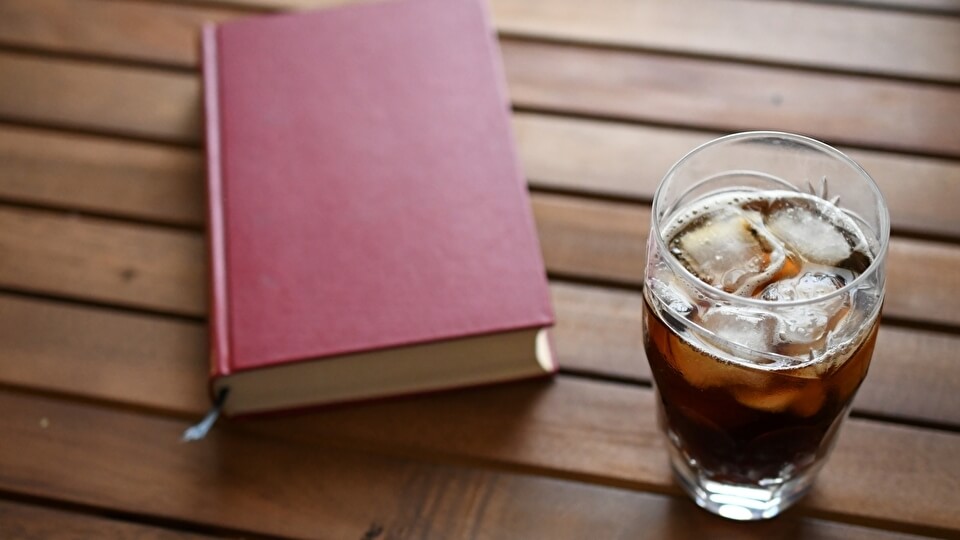










コメント