戦い方のポイント
今回から、前回の第3図以下の戦い方を説明していきます(第1図として改めて掲載します)。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・ ・ ・v桂v香|一 | ・ ・ ・v飛 ・v金v王 ・ ・|二 |v歩v歩v歩 ・v歩v歩 ・v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・ ・v銀v角 ・ ・|四 | ・ ・ 歩v銀 ・ ・v歩 ・ ・|五 | ・ 歩 ・v歩 ・ 歩 ・ ・ ・|六 | 歩 ・ 銀 ・ 歩 銀 歩 歩 歩|七 | 角 ・ ・ 飛 金 ・ 金 王 ・|八 | 香 桂 ・ ・ ・ ・ ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:歩 手数=37 ▲3八金まで
手が広い局面のため、後手がこれから説明する手順のように指してくるとは限らないでしょう。しかし、ポイントをおさえておけばどう指されても応用が利くのではないかと思います。
そのポイントとは、以下の通りです。
- 8筋から仕掛けられるようにしておく
- 玉頭攻めを仕掛ける
- 相手の角道を止める
- 8筋から仕掛ける
さて第2図は、第1図から後手が△5二金上とした局面。玉を固める自然な一手です。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・ ・ ・ ・ ・v桂v香|一 | ・ ・ ・v飛v金v金v王 ・ ・|二 |v歩v歩v歩 ・v歩v歩 ・v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・ ・v銀v角 ・ ・|四 | ・ ・ 歩v銀 ・ ・v歩 ・ ・|五 | ・ 歩 ・v歩 ・ 歩 ・ ・ ・|六 | 歩 ・ 銀 ・ 歩 銀 歩 歩 歩|七 | 角 ・ ・ 飛 金 ・ 金 玉 ・|八 | 香 桂 ・ ・ ・ ・ ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:歩 手数=38 △5二金まで
後手からは手が出せず、先手からも手は出しにくく、しばらく第2次駒組み合戦の様相を呈しています・・・が、ここから先手は上述のポイントに沿って手を作っていきます。
第2図以下の指し手
▲1六歩 △1四歩
▲8五歩 △2四歩
▲4五歩! (第3図)
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・ ・ ・ ・ ・v桂v香|一 | ・ ・ ・v飛v金v金v王 ・ ・|二 |v歩v歩v歩 ・v歩v歩 ・ ・ ・|三 | ・ ・ ・ ・ ・v銀v角v歩v歩|四 | ・ 歩 歩v銀 ・ 歩v歩 ・ ・|五 | ・ ・ ・v歩 ・ ・ ・ ・ 歩|六 | 歩 ・ 銀 ・ 歩 銀 歩 歩 ・|七 | 角 ・ ・ 飛 金 ・ 金 玉 ・|八 | 香 桂 ・ ・ ・ ・ ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:歩 手数=43 ▲4五歩まで
玉頭攻め
後手の△2四歩は△2三角と引く余地を作った手で、価値の高い手といえます。
対して先手は、▲8五歩と8筋をつめた後、いきなり開戦の▲4五歩!一見タダで歩を差し出したような手ですが、3・4筋で大きなポイントを稼ぐことができます。
なおこの手に代わり▲8四歩△同歩▲8二歩は、後手の角筋を活かした攻め合い△6七歩成で、先手不満。本譜のほうが勝ります。
さて▲4五歩に対し、△5五銀では中途半端に銀がうわずるだけで、△3三銀では▲4六銀で簡単に押さえ込まれてしまうので、応手は①△4五同銀か②△4五同角の2つに絞られます。
まず①△4五同銀(第4図)について説明していきます。
後手の持駒:歩 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・ ・ ・ ・ ・v桂v香|一 | ・ ・ ・v飛v金v金v王 ・ ・|二 |v歩v歩v歩 ・v歩v歩 ・ ・ ・|三 | ・ ・ ・ ・ ・ ・v角v歩v歩|四 | ・ 歩 歩v銀 ・v銀v歩 ・ ・|五 | ・ ・ ・v歩 ・ ・ ・ ・ 歩|六 | 歩 ・ 銀 ・ 歩 銀 歩 歩 ・|七 | 角 ・ ・ 飛 金 ・ 金 玉 ・|八 | 香 桂 ・ ・ ・ ・ ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:歩 手数=44 △4五同銀まで
①△4五歩の変化
一歩損した上、後手の銀に5段目まで進出され、先手陣玉頭は一見押さえ込まれたようですが、△4六歩と打たれるわけではない(二歩!)ので問題ありません。
第4図の局面は、後手の銀を引っ張り込んで角道を止めることに成功した、と考えることができます。角道が止まった今がチャンスです。
第4図以下の指し手
▲8四歩 △同 歩
▲8二歩 (第5図)
後手の持駒:歩二 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・ ・ ・ ・ ・v桂v香|一 | ・ 歩 ・v飛v金v金v王 ・ ・|二 |v歩 ・v歩 ・v歩v歩 ・ ・ ・|三 | ・v歩 ・ ・ ・ ・v角v歩v歩|四 | ・ ・ 歩v銀 ・v銀v歩 ・ ・|五 | ・ ・ ・v歩 ・ ・ ・ ・ 歩|六 | 歩 ・ 銀 ・ 歩 銀 歩 歩 ・|七 | 角 ・ ・ 飛 金 ・ 金 玉 ・|八 | 香 桂 ・ ・ ・ ・ ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=47 ▲8二歩まで
このタイミングで▲8四歩~▲8二歩ならば、前項で述べた△6七歩成のような後手から暴れる手段がないので、桂を取りにいってわかりやすく先手良しです。なお、▲8二歩に対し△同飛は、もちろん▲6五角!で先手大優勢。後手は、右銀が常に質駒でかつ負担になっているのがつらいところです。
なお、▲8二歩のところ次回説明する▲8八飛〜▲6八銀でも先手良しです。
次回は、本筋の②△4五同角以下の展開について説明します。

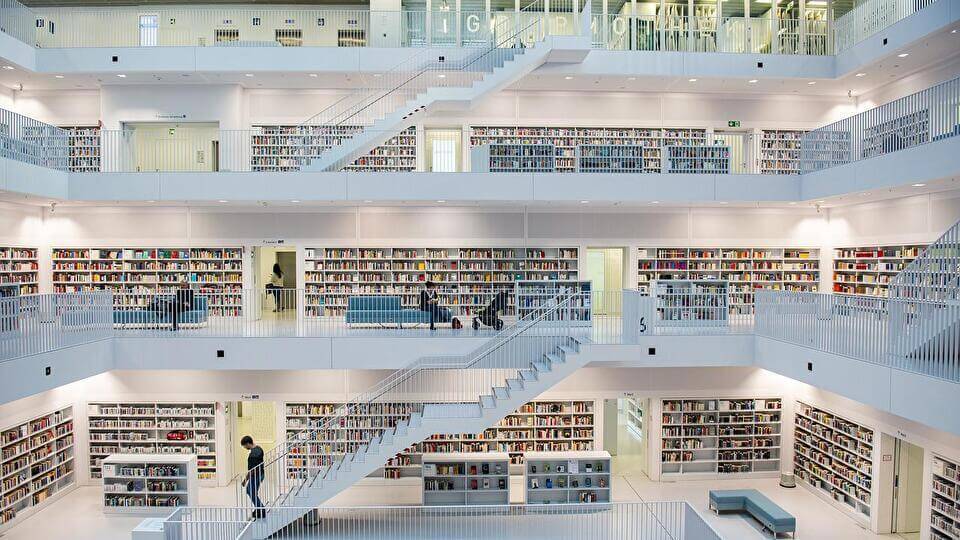
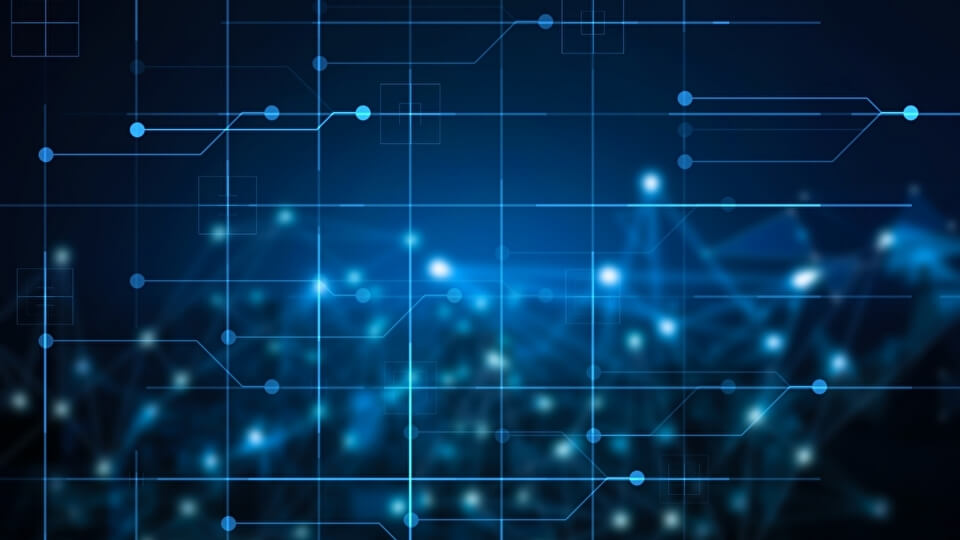
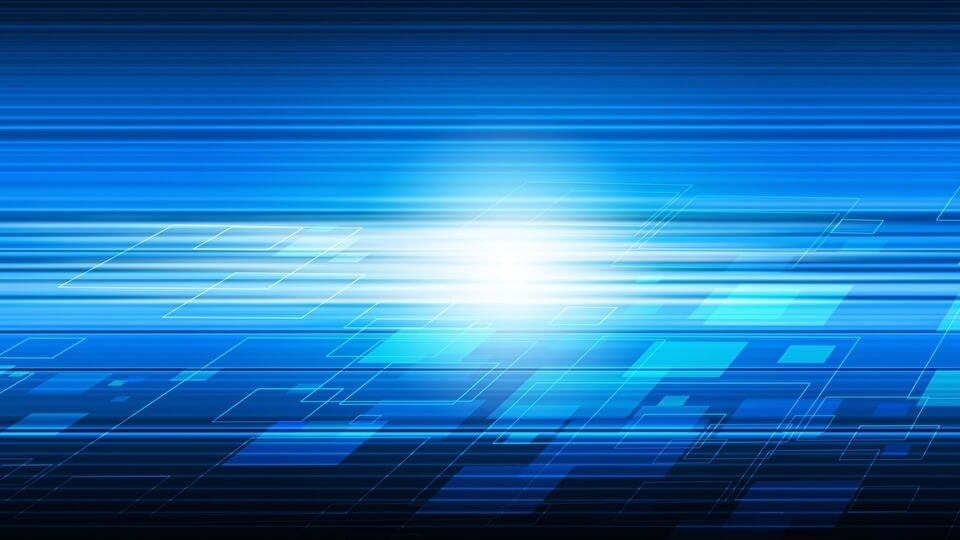
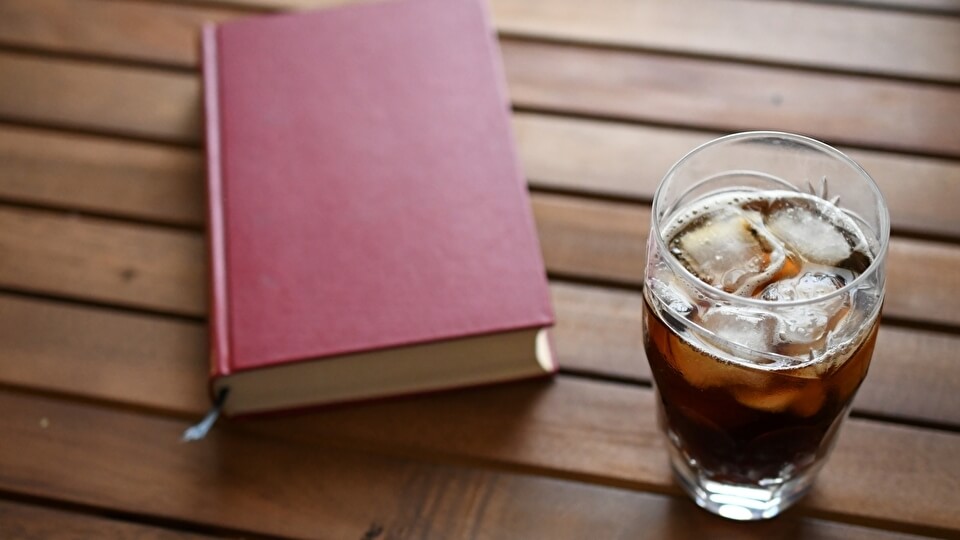







コメント