レアケースな陽動居飛車型
第4節では、陽動居飛車型を説明します。
先手の5手目▲2八銀を見て、後手△8四歩(第1図)。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂v銀v金v王v金v銀v桂v香|一 | ・v飛 ・ ・ ・ ・ ・v角 ・|二 |v歩 ・v歩v歩v歩v歩 ・v歩v歩|三 | ・v歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・|五 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 歩 歩 歩 歩 歩 歩 歩|七 | ・ 角 飛 ・ ・ 王 ・ 銀 ・|八 | 香 桂 銀 金 ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=6 △8四歩まで
後手としては相当△8四歩は指しにくいはずです。なぜなら一手前の△3五歩で「相振りにしよう」と決意しているわけですから。
したがって、先手の▲2八銀を見てこれを積極的にとがめにいこうと思い付く敏感な序盤感覚の持ち主か、もしくはたまたまこのホームページを見ていて、こういう展開もあることを知っている人が相手でないと、ありえない戦型かもしれません。
しかし、この「陽動居飛車型」は猫だまし側としては結構気がかりな戦型です。
この段階では、伸びすぎの△3五歩と壁形の▲2八銀とは「見合い」ですが、持久戦模様になってしまうと△3五歩は立派な「3筋の位」として活きてきます。
それもまた一局でしょうが、先手としてはどんどん動いていき、早めに3五の歩をとがめにいくのが優位に進める1つの手段といえます。
ここではそういった指し回しを紹介します。
7筋の歩を突いていく
第1図から、数手はほぼ必然の手順といえます。
第1図以下の指し手
▲7六歩 △8五歩
▲7五歩 (第2図)
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂v銀v金v王v金v銀v桂v香|一 | ・v飛 ・ ・ ・ ・ ・v角 ・|二 |v歩 ・v歩v歩v歩v歩 ・v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四 | ・v歩 歩 ・ ・ ・v歩 ・ ・|五 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 ・ 歩 歩 歩 歩 歩 歩|七 | ・ 角 飛 ・ ・ 王 ・ 銀 ・|八 | 香 桂 銀 金 ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=9 ▲7五歩まで
第3章「2手目△3四歩/VS居飛車型」で紹介したように、超序盤戦なら7五まで突かずに▲7六歩のままでも8筋を受けることはできますが、第1図では2八の壁銀が気になります。
第2図のように▲7五歩まで進めると、以下△8六歩には▲同歩△同飛▲7四歩!△同歩▲2二角成△同銀▲9五角!の王手飛車があり、より強力に8筋の攻めに対して反発できるので、さっさと7筋は突いてしまったほうがよいと思います。
△8五歩をすぐに突いてこなかった場合
ただし後手が上記手順中△8五歩を突いてこなかった場合は、▲7五歩の代わりに▲6六歩と角道を止め、8筋は普通に▲7七角で受け、以下▲3九(5九)玉~▲2六歩~▲2七銀~▲3八飛(参考図) のような袖飛車の逆襲で3筋をとがめにいくのも面白いかもしれません。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・ ・ ・v金v銀v桂v香|一 | ・v飛 ・v銀v金 ・v王v角 ・|二 |v歩 ・v歩v歩 ・v歩 ・v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・ ・ ・|四 | ・v歩 ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・|五 | ・ ・ 歩 歩 ・ ・ ・ 歩 ・|六 | 歩 歩 角 ・ 歩 歩 歩 銀 歩|七 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ 飛 ・ ・|八 | 香 桂 銀 金 ・ 金 王 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=19 ▲3八飛まで
このような変化を避けるためにも、後手は第2図のように△8五歩と形を決めにくる可能性が高いと考えられます。
さて、あいかわらず右辺の3五歩と2八銀の形に違和感が残る第2図。
次回に続きます。
次回


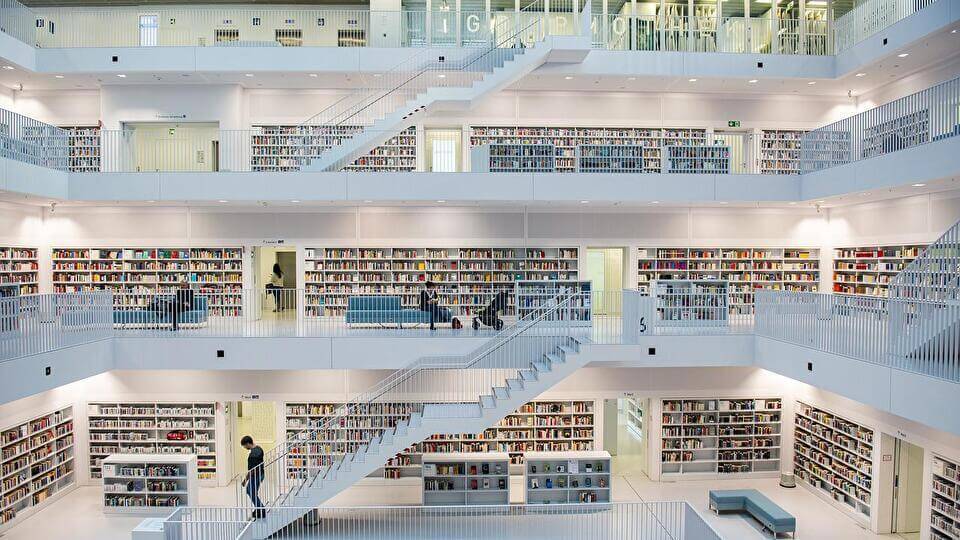
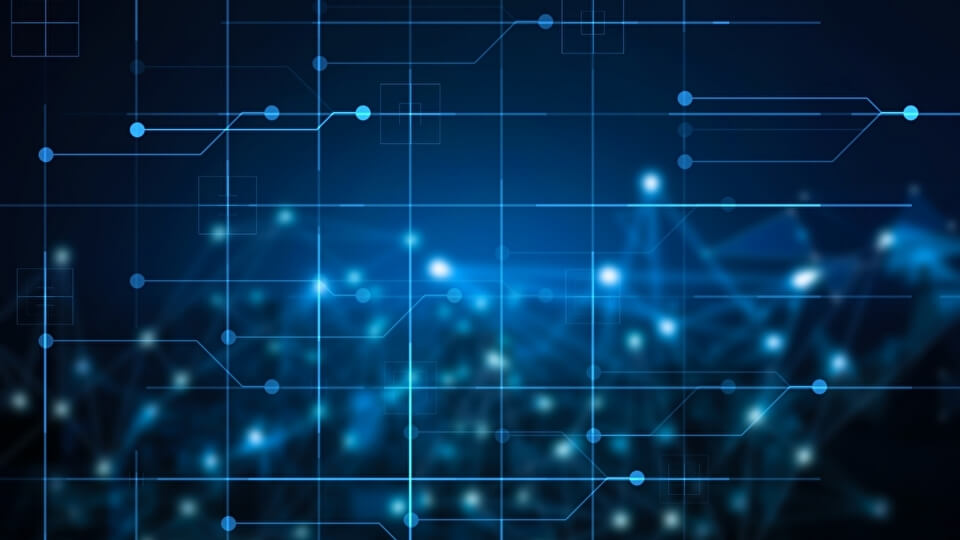
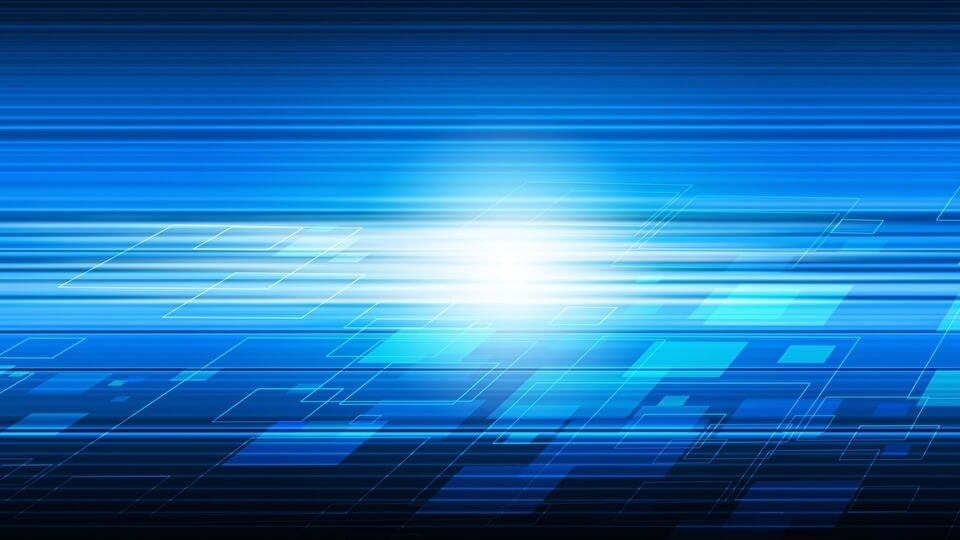
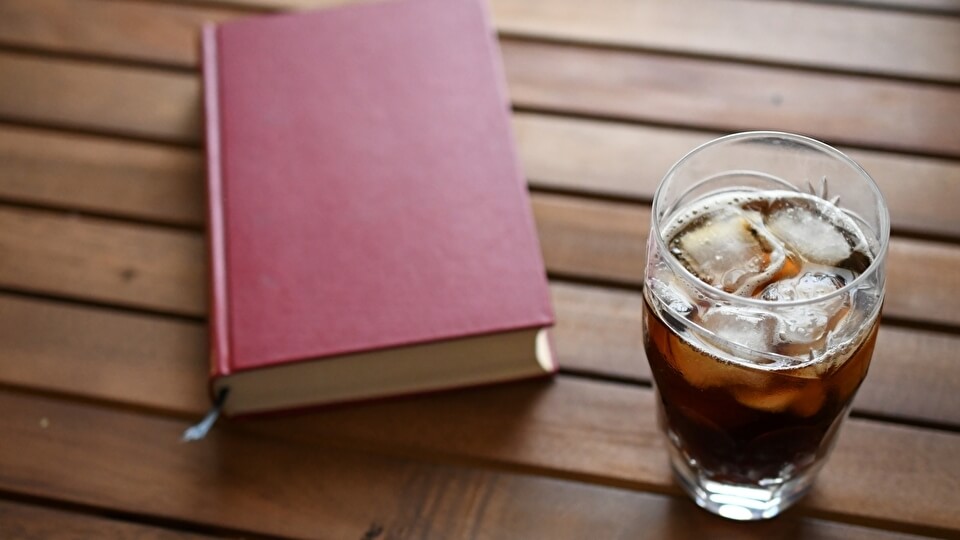







コメント