飛車を1つ寄って戦う
「袖飛車」とは、飛車を居飛車の位置から1つ寄って戦う戦術です(第1図)。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・v金 ・v桂v香|一 | ・ ・v飛 ・ ・v銀v王v角 ・|二 |v歩 ・v歩v銀 ・v歩 ・v歩 ・|三 | ・ ・ ・v歩v歩 ・v歩 ・v歩|四 | ・v歩 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ 飛 歩 ・ ・ ・ ・ 歩|六 | 歩 歩 ・ 銀 歩 歩 歩 歩 ・|七 | ・ 角 ・ ・ ・ ・ 銀 王 ・|八 | 香 桂 ・ 金 ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=0 △7二飛まで
第1図は先手石田流三間飛車VS後手袖飛車の例ですが、石田流に限らずどんな振り飛車が相手でも、または相居飛車戦でも、飛車を1つ寄った形は袖飛車と呼ばれます。
以下は三間飛車に絞って説明します。
対ノーマル三間飛車は稀
袖飛車は、対ノーマル三間飛車で採用されることは比較的稀(まれ)です。なぜなら、もともと三間飛車が待ち構えている筋であるため効率が良い攻めとは見られていないからです。
それでも採用されることがないわけではありません。最近の一例としては、例えば2018年11月に行われた第90期ヒューリック杯棋聖戦一次予選(主催:産経新聞社、日本将棋連盟)、▲西田拓也四段 対 △大橋貴洸四段戦(第2図)が挙げられます。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・ ・v金 ・v金v桂v香|一 | ・ ・v飛v銀 ・v銀v王v角 ・|二 | ・ ・ ・v歩 ・v歩 ・v歩 ・|三 |v歩 ・v歩 ・v歩 ・v歩 ・v歩|四 | ・v歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ 歩 歩 歩 歩 ・ ・ 歩|六 | 歩 歩 角 ・ ・ 金 歩 歩 ・|七 | ・ ・ 飛 銀 ・ ・ 銀 王 ・|八 | 香 桂 ・ ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=0 △7二飛まで
今風のエルモ囲い+袖飛車の布陣で、以下6筋で先手が銀を上がり後手が歩を突いたあと、先手は角の斜め移動、後手は飛車の横移動を繰り返して千日手となりました。
対石田流のところでも説明しますが、袖飛車は千日手狙いの要素も含んでいます。
対石田流は定跡化も
ノーマル三間飛車に対し効率が良くないと見られている袖飛車ですが、単騎で浮き飛車に構える石田流に対しては、袖飛車と6三の銀で素早くかつ手厚く相手の飛車を責められるので有力、と見られています。
6三だけでなく5三にも銀を配置した二枚銀袖飛車(第3図)ならばさらに手厚くなります。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・ ・ ・v桂v香|一 | ・ ・v飛 ・ ・v金v王v角 ・|二 | ・ ・v歩v銀v銀v歩 ・v歩 ・|三 |v歩 ・ ・v歩v歩 ・v歩 ・v歩|四 | ・v歩 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | 歩 ・ 飛 歩 ・ ・ ・ ・ 歩|六 | ・ 歩 桂 銀 歩 歩 歩 歩 ・|七 | ・ 角 ・ ・ 金 ・ 銀 王 ・|八 | 香 ・ ・ ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=0 △7二飛まで
後述するように、石田流VS袖飛車を解説した戦術書もいくつか存在していて、定跡化が比較的進んでいます。
▲9七角の石田流本組みで7五の地点をケアするのが石田流の常套手段ですが、袖飛車側から7筋と9筋を絡めた仕掛けがあったり、場合によっては△9二飛(第4図。△9五歩からの端攻めを狙う)▲7九角△7二飛!▲9七角(7五の地点を守る)△9二飛!▲7九角・・・の千日手狙いも成立します。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・ ・ ・ ・ ・v桂v香|一 |v飛 ・ ・ ・v金 ・v金v王 ・|二 | ・ ・v歩v銀v歩v歩v角v銀 ・|三 |v歩 ・ ・v歩 ・ ・v歩v歩v歩|四 | ・v歩 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | 歩 ・ 飛 歩 銀 歩 ・ ・ 歩|六 | 角 歩 桂 ・ 歩 ・ 歩 歩 ・|七 | ・ ・ ・ ・ 金 ・ 銀 王 ・|八 | 香 ・ ・ ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=0 △9二飛まで
第4図では▲8五桂や▲6五歩から暴れたくなりますが、後手玉が堅い銀冠のため難局になります(船囲いならば成立しやすくなります)。
そのため相手の囲いや形に応じて▲9七角型でなく▲7七角型(第5図)にしたり▲7八金型(第6図)にしたりして、仕掛けられた直後に▲6五歩からさばきにいくような対袖飛車戦術も生まれており、いずれも有力です。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・ ・ ・v金v王v桂v香|一 | ・ ・v飛 ・v金 ・v銀v角 ・|二 |v歩 ・v歩v銀v歩v歩 ・v歩v歩|三 | ・ ・ ・v歩 ・ ・v歩 ・ ・|四 | ・v歩 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ 飛 歩 ・ ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 角 銀 歩 歩 歩 歩 歩|七 | ・ ・ ・ ・ 金 ・ 銀 ・ ・|八 | 香 桂 ・ ・ ・ 金 王 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=0 ▲7七角まで
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・v金 ・v桂v香|一 | ・ ・v飛 ・ ・v銀v王v角 ・|二 |v歩 ・v歩v銀 ・v歩 ・v歩 ・|三 | ・ ・ ・v歩v歩 ・v歩 ・v歩|四 | ・v歩 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ 飛 歩 ・ ・ ・ ・ 歩|六 | 歩 歩 ・ 銀 歩 歩 歩 歩 ・|七 | ・ 角 金 ・ ・ ・ 銀 王 ・|八 | 香 桂 ・ ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=0 ▲7八金まで
対袖飛車を解説している棋書
対袖飛車を解説している三間飛車の棋書としては、例えば「石田流を指しこなす本【急戦編】」(戸辺誠七段 著)、「石田流の基本―本組みと7七角型」(同じく戸辺誠七段 著)、「よくわかる石田流」(高崎一生六段 著)などが挙げられます。
これらのうち、第1図のような船囲い+袖飛車急戦が載っているのは「石田流を指しこなす本【急戦編】」と「よくわかる石田流」。第4図のような△3一金型左美濃+袖飛車急戦が載っているのは「石田流の基本―本組みと7七角型」のみ。そして第3図のような二枚銀袖飛車は3冊すべてに載っています。
まとめ
対石田流で定跡化している袖飛車戦法。対棒金と同じく、無策でいると押さえ込まれて手も足も出なくなるので、定跡書などを読んで、相手の布陣に相性の良い石田流の構え、およびさばきの手筋を覚えておくと良いでしょう。
関連記事


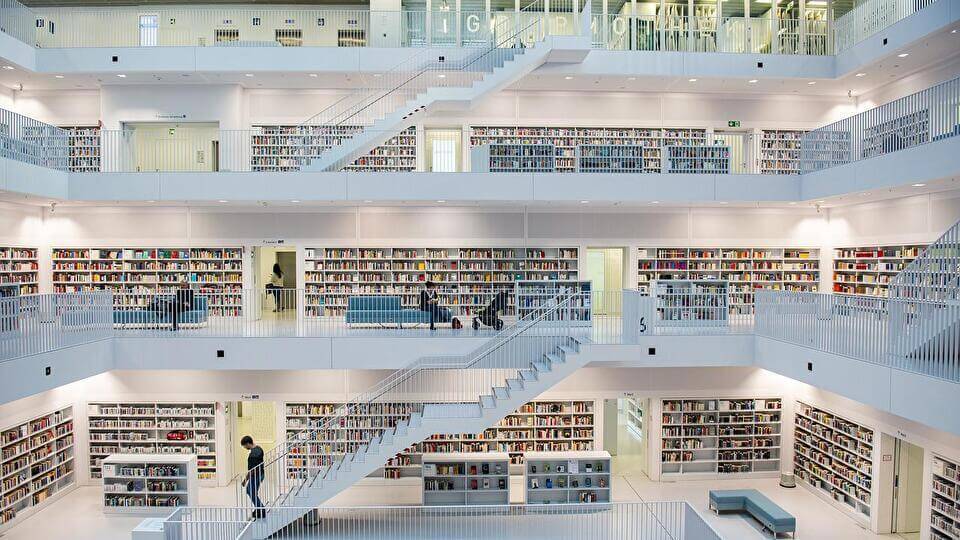
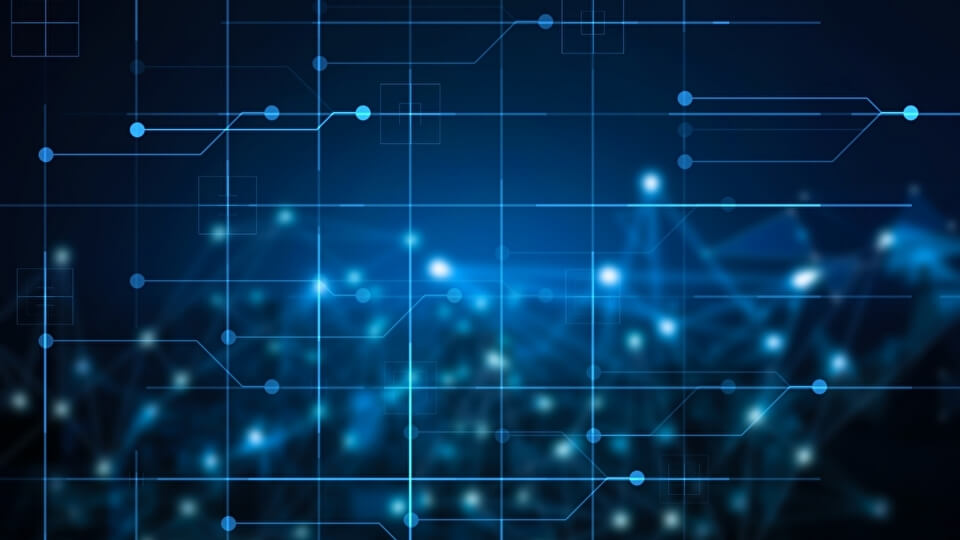
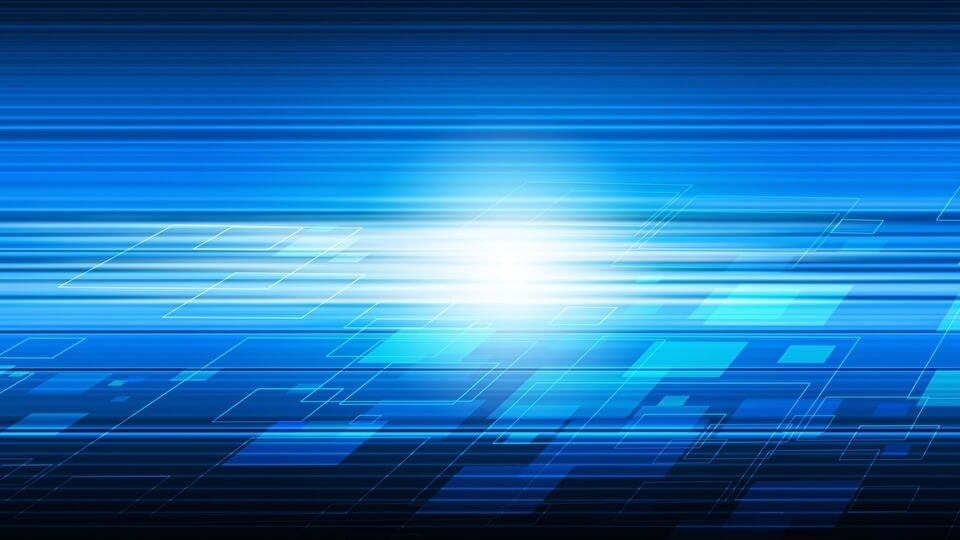
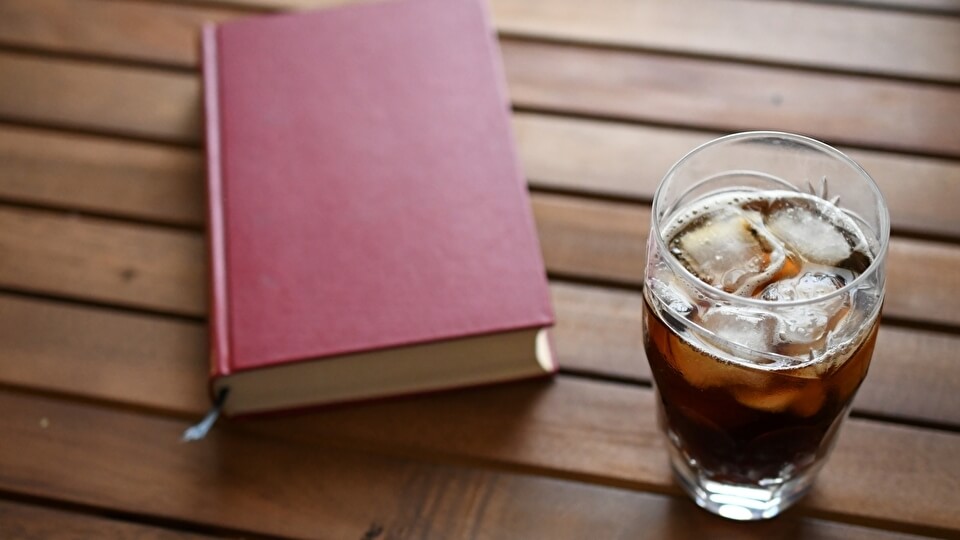





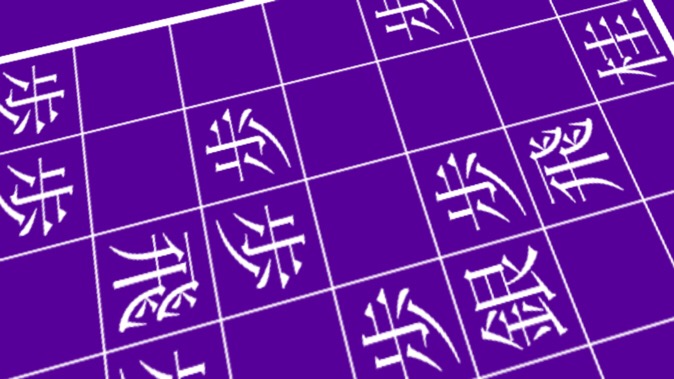





コメント