角交換しない▲9七角型石田流
「石田流本組み」とは、角交換しない▲9七角・▲7七桂型石田流です(第1図)。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・ ・ ・v金 ・v桂v香|一 | ・ ・ ・ ・v金 ・v銀v角 ・|二 | ・ ・v歩v銀v歩v歩 ・v王 ・|三 |v歩v飛 ・v歩 ・ ・v歩v歩v歩|四 | ・v歩 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | 歩 ・ 飛 歩 ・ ・ ・ ・ 歩|六 | 角 歩 桂 銀 歩 歩 歩 歩 ・|七 | ・ ・ ・ ・ 金 ・ 銀 王 ・|八 | 香 ・ ・ ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=31 ▲5八金左まで
攻守に優れた美しい布陣です。
石田流本組みの特徴として、以下が挙げられます(石田流側を先手としています)。
- 角交換無し
- ▲6六歩型
- ▲9七角・▲7七桂型
早い段階で▲6六歩と突いて角交換が起こらないようにしてから、▲7六飛で8筋を受け、その後▲9七角、▲7七桂と上がります。角上がりと桂上がりの順番はケースバイケースです。
美濃囲いが基本
囲いには特に規定はありませんが、バランスを考慮し美濃囲いにするのが一般的です。これは石田流のすべての形に当てはまります。
振り飛車穴熊(参考1図)は、囲いが右辺に偏りすぎ(金が5筋・4筋ではなく、2枚とも3筋にくる、ということ) なきらいがあり、駒がうわずった軽い形である石田流とは相性があまりよくありません。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・ ・ ・ ・v金v桂v王|一 | ・ ・ ・ ・ ・v金 ・v銀v香|二 | ・ ・v歩v歩v銀v歩v角v歩v歩|三 |v歩v飛 ・ ・v歩 ・v歩 ・ ・|四 | ・v歩 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | 歩 ・ 飛 歩 ・ ・ ・ ・ ・|六 | 角 歩 桂 銀 歩 歩 歩 歩 歩|七 | ・ ・ ・ ・ ・ 金 ・ 銀 香|八 | 香 ・ ・ ・ ・ ・ 金 桂 王|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=37 ▲4八金左まで
したがって石田流+穴熊は、上級者向きの布陣です。
2通りの組み方
このあと説明していく通り、石田流本組みに組むには1手の違いが大きいため、後手番で組むのは非常に困難です。したがって、以下先手番の立場で説明します。
また、初手▲7六歩に対し2手目△8四歩とされても石田流本組みに組むのはほぼ無理になるので、2手目は△3四歩に限定して説明します。
石田流本組みは、大きく分けて2通りの組み方があります。1つ目は3手目▲7五歩から、2つ目は3手目▲6六歩からです。
3手目▲7五歩からの石田流本組み
まず、3手目▲7五歩(第2図)からの石田流本組みについて説明します。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂v銀v金v王v金v銀v桂v香|一 | ・v飛 ・ ・ ・ ・ ・v角 ・|二 |v歩v歩v歩v歩v歩v歩 ・v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・|四 | ・ ・ 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 ・ 歩 歩 歩 歩 歩 歩|七 | ・ 角 ・ ・ ・ ・ ・ 飛 ・|八 | 香 桂 銀 金 王 金 銀 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=3 ▲7五歩まで
3手目▲7五歩は、3手目にして石田流を明示する一手です。
ここから△8八角成か△8四歩以外の手ならば、石田流本組みに組むことができます。
石田流本組みは角交換しない石田流なので、△8八角成とされると論外です。
△8四歩とされた場合は、以下▲6六歩と突いてしまうと△8五歩(第3図)とされ、▲7七角と上がって受けざるを得なくなります。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂v銀v金v王v金v銀v桂v香|一 | ・v飛 ・ ・ ・ ・ ・v角 ・|二 |v歩 ・v歩v歩v歩v歩 ・v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・|四 | ・v歩 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ ・ 歩 ・ ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 ・ ・ 歩 歩 歩 歩 歩|七 | ・ 角 ・ ・ ・ ・ ・ 飛 ・|八 | 香 桂 銀 金 王 金 銀 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=6 △8五歩まで
かといって▲7八飛と回るとやはり△8五歩(第4図)とされ▲6六歩と突く余裕がありません。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂v銀v金v王v金v銀v桂v香|一 | ・v飛 ・ ・ ・ ・ ・v角 ・|二 |v歩 ・v歩v歩v歩v歩 ・v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・|四 | ・v歩 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 ・ 歩 歩 歩 歩 歩 歩|七 | ・ 角 飛 ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 | 香 桂 銀 金 王 金 銀 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=6 △8五歩まで
これは石田流本組みではなく主に角交換型の石田流である「升田式石田流」に進む展開となります。

なお第4図以下▲7六飛には△8八角成▲同銀△4五角があります。
一方で、3手目▲7五歩に対し△8八角成か△8四歩以外の手、例えば△6二銀ならば、▲6六歩として以下△8四歩とされても▲7八飛△8五歩▲7六飛(第5図)でぴったり間に合います。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金v王v金v銀v桂v香|一 | ・v飛 ・v銀 ・ ・ ・v角 ・|二 |v歩 ・v歩v歩v歩v歩 ・v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・|四 | ・v歩 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ 飛 歩 ・ ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 ・ ・ 歩 歩 歩 歩 歩|七 | ・ 角 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 | 香 桂 銀 金 王 金 銀 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=9 ▲7六飛まで
3手目▲6六歩からの石田流本組み
続いて3手目▲6六歩(第6図)からの石田流本組みについて説明します。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂v銀v金v王v金v銀v桂v香|一 | ・v飛 ・ ・ ・ ・ ・v角 ・|二 |v歩v歩v歩v歩v歩v歩 ・v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ 歩 歩 ・ ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 ・ ・ 歩 歩 歩 歩 歩|七 | ・ 角 ・ ・ ・ ・ ・ 飛 ・|八 | 香 桂 銀 金 王 金 銀 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=3 ▲6六歩まで
ここから△8四歩以外の手ならば、石田流本組みに組むことができます。
△8四歩と突かれると▲7八飛と回っても△8五歩とさらに突かれ、▲7七角と上がらざるを得なくなります(△8五歩と突かれなければ▲7五歩から▲7六飛が間に合います)。
組めても組みにくい石田流本組み
以上の条件を成立させ、角道を止めて角を8八に置いたまま飛車を浮く形に組むことができたとしても、そのあと石田流本組みの▲9七角型に組むべきかと言われると、実はそうとも言い切れません。居飛車側の布陣によります。
例えば石田流対策の有力戦法の1つである「棒金戦法」を居飛車が採用してきた場合、石田流側はできるだけ▲9七角と上がる手を保留したほうが良いとされています。例えば以下の記事を参照ください。

また、同じく対石田流の有力戦法の1つである「△3一玉型左美濃」を居飛車が採用してきた場合も、▲9七角型ではなく▲7七角型(第7図)の方が有力とされています。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・ ・ ・v金v王v桂v香|一 | ・v飛 ・ ・v金 ・v銀 ・ ・|二 |v歩 ・v歩v銀v歩v歩v角v歩 ・|三 | ・ ・ ・v歩 ・ ・v歩 ・v歩|四 | ・v歩 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ 飛 歩 ・ ・ ・ ・ 歩|六 | 歩 歩 角 銀 歩 歩 歩 歩 ・|七 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 王 ・|八 | 香 桂 ・ 金 ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=25 ▲7七角まで
名もなき石田流
以上のように、石田流本組みが実戦で生じるケースは今では稀になりました。
しかし、早々に角道をとめて▲7七角と上がるノーマル三間飛車に対し居飛車が持久戦にしてきたときに、▲7五歩と突いて▲6八角や▲5九角と角を右側に引いてから石田流に組む「名もなき石田流」は数多く指されています。
例えば以下の記事を参照下さい。

石田流本組みまでの手順
石田流本組みまでの手順の一例を紹介します。第8図は、居飛車側が△8五歩と飛車先を詰めず△6二銀と上がったところです。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金v王v金v銀v桂v香|一 | ・v飛 ・v銀 ・ ・ ・v角 ・|二 |v歩 ・v歩v歩v歩v歩 ・v歩v歩|三 | ・v歩 ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ 歩 歩 ・ ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 ・ ・ 歩 歩 歩 歩 歩|七 | ・ 角 飛 ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 | 香 桂 銀 金 王 金 銀 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=6 △6二銀まで
第8図以下の指し手
▲7五歩 △8五歩
▲7六飛 (第9図)
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金v王v金v銀v桂v香|一 | ・v飛 ・v銀 ・ ・ ・v角 ・|二 |v歩 ・v歩v歩v歩v歩 ・v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・|四 | ・v歩 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ 飛 歩 ・ ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 ・ ・ 歩 歩 歩 歩 歩|七 | ・ 角 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 | 香 桂 銀 金 王 金 銀 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=9 △7六飛まで
後手が8筋を詰めてこなかったおかげで▲7七角は不要となり、▲7五歩と突けます。この後に△8五歩とされても、▲7六飛と上がれば飛車の横利きで△8六歩を受けることができます。
以下、囲いを急がず一直線に石田流本組みを目指したときの一例が下記の手順です。
第9図以下の指し手
△6四歩
▲7七桂 △6三銀
▲9六歩 △9四歩
▲9七角 △4二玉
▲7八銀 △3二玉
▲6七銀 (第10図)
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・v金v銀v桂v香|一 | ・v飛 ・ ・ ・ ・v王v角 ・|二 | ・ ・v歩v銀v歩v歩 ・v歩v歩|三 |v歩 ・ ・v歩 ・ ・v歩 ・ ・|四 | ・v歩 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | 歩 ・ 飛 歩 ・ ・ ・ ・ ・|六 | 角 歩 桂 銀 歩 歩 歩 歩 歩|七 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 | 香 ・ ・ 金 王 金 銀 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=19 △6七銀まで
攻守に優れた布陣
角の利きは、7五の地点をサポートしつつ、6四・5三の地点への攻めをにらんでいます。飛車の利きは、7五と6六の歩を捌けば縦横無尽。角の頭(9六の地点)をケアしてもいます。
また、振り飛車の陣形では珍しく左桂を跳ねているのも特徴的で、戦いが始まると▲6五(8五)桂~▲5三(7三)桂成とうまくさばける可能性が高いといえます。
ただしこの順は、あくまでも参考です。こんなに早く石田流本組みを目指してしまっては、 後手の方がそこそこの将棋定跡通であれば棒金戦法にされ、石田流側は痛い目に会うでしょう。
第10図から、後手が棒金を狙わず持久戦を目指してきた場合の一例が第11図。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・ ・ ・v金 ・v桂v香|一 | ・ ・ ・ ・v金 ・v銀v角 ・|二 | ・ ・v歩v銀v歩v歩 ・v王 ・|三 |v歩v飛 ・v歩 ・ ・v歩v歩v歩|四 | ・v歩 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | 歩 ・ 飛 歩 ・ ・ ・ ・ 歩|六 | 角 歩 桂 銀 歩 歩 歩 歩 ・|七 | ・ ・ ・ ・ 金 ・ 銀 王 ・|八 | 香 ・ ・ ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=31 ▲5八金左まで
もちろん一局ですが、ここまで綺麗に石田流本組みが組めればこの先気分よく戦えるのではないでしょうか。
関連記事、関連棋書


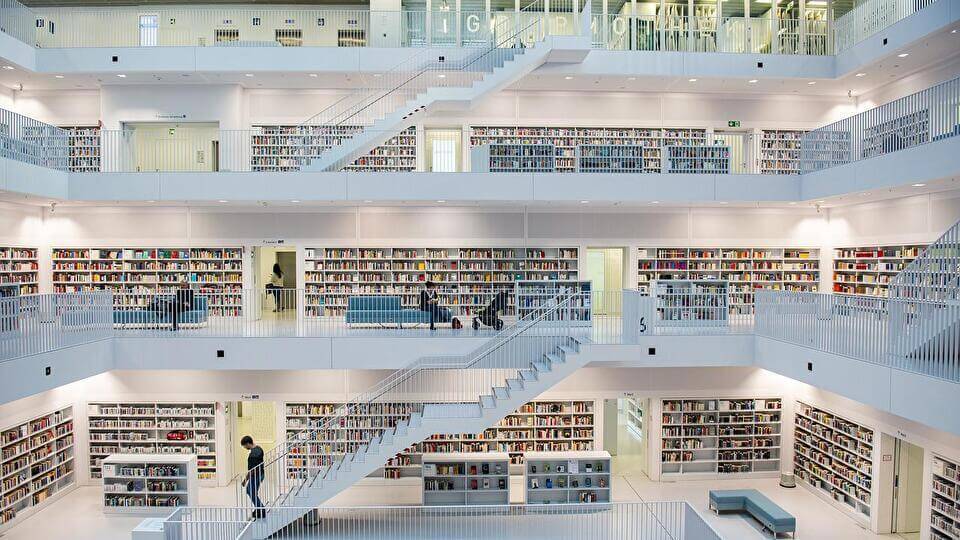
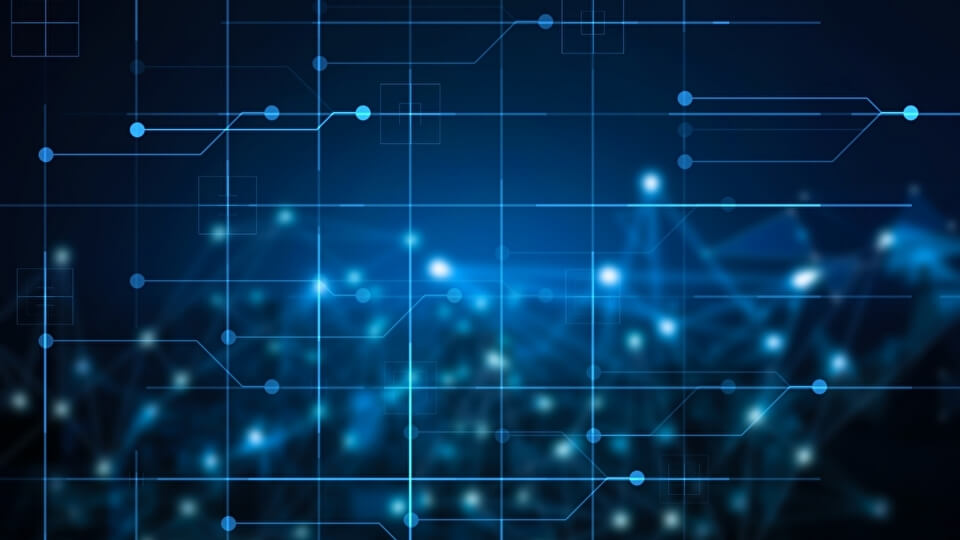
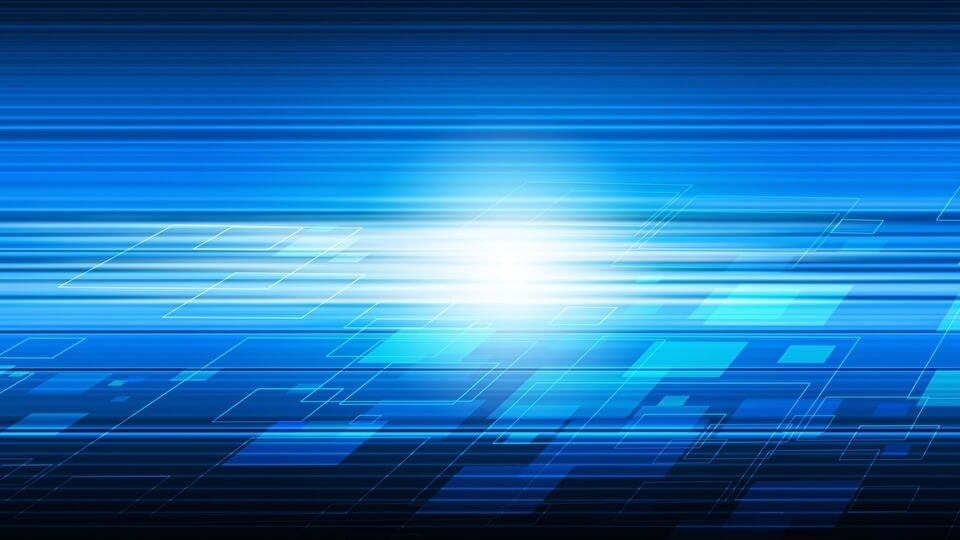
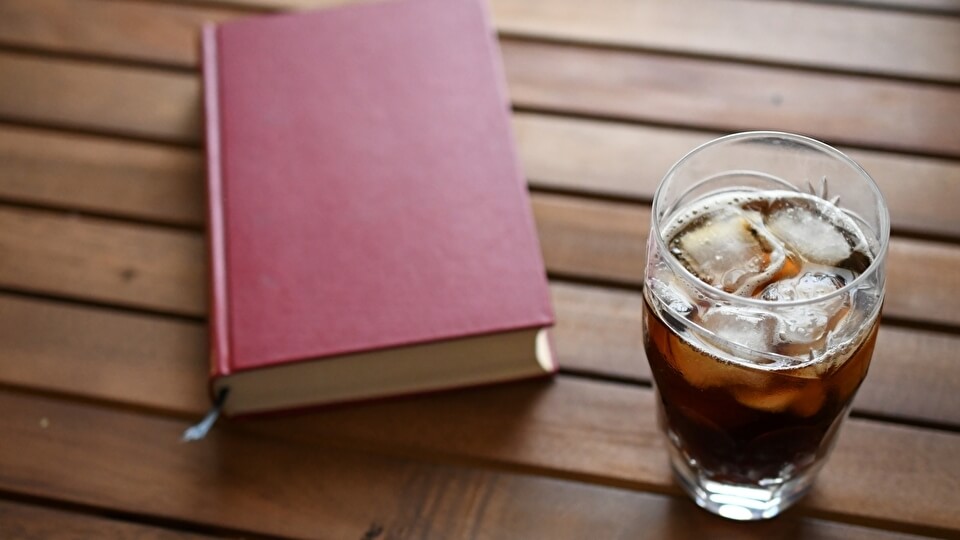







コメント