角道を開けずに平美濃に囲う戦法
「飯島流引き角戦法」とは、居飛車対振り飛車の対抗形で居飛車が採用する、角道を開けずに引き角(△3一角)にし、△5三角(または△6四角)としてから左美濃に囲う戦法です(第1図)。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・v金v王v桂v香|一 | ・v飛 ・v銀 ・ ・v銀 ・ ・|二 |v歩 ・v歩v歩v角v歩v歩v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・ ・ ・|四 | ・v歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ 歩 銀 歩 ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 角 歩 ・ 歩 歩 歩 歩|七 | ・ ・ 飛 ・ ・ ・ 王 ・ ・|八 | 香 桂 ・ 金 ・ 金 銀 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=0 △3一玉まで
△3四歩を突いていない、平美濃囲いに組むのが特徴です。基本的に後手番の戦法ですが、先手番でも採用することができます。
升田幸三賞受賞戦法
飯島流引き角戦法は、プロ棋界にて藤井システム対策として三浦弘行九段が創案した作戦を、飯島栄治七段が研究し大きく発展させた戦法です。飯島七段はこの戦法を一度ならず多数採用し、結果も残しています。
もともと同様の戦術が「平美濃返し」という呼び名で棋書「将棋・B級戦法の達人」で解説されていましたが、これをプロ棋戦で採用しようという三浦九段の冒険心と、さらに「栄級」戦法、もといA級戦法に昇華させようという飯島七段の求道心には感銘を受けます。
飯島七段はこの戦法で、2010年の第37回将棋大賞の升田幸三賞を受賞しました。
最初に指した三浦九段もさすがですが、多用し結果を残したことの方がより評価された格好と言えるでしょう。

飯島流の特徴
飯島流引き角戦法の特徴を挙げると、例えば以下の通りです。
- 振り飛車の美濃囲いと同じ形
- 藤井システムと角交換振り飛車を避けられる
- 飛車と角による飛車先速攻
- 持久戦狙い
振り飛車の美濃囲いと同じ形
一番の特徴はこれでしょう。
振り飛車は玉頭の歩を突かない「平美濃囲い」にまずは囲うのに対し、普通居飛車は対局直後に△3四歩と突いているので、左美濃に組んでも振り飛車と同じ美濃囲いにはなりません(参考1図)。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・ ・ ・v金 ・v桂v香|一 | ・ ・ ・ ・v金 ・v銀v王 ・|二 | ・ ・v歩v銀 ・v歩v角 ・ ・|三 |v歩v飛 ・v歩v歩 ・v歩v歩v歩|四 | ・v歩 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | 歩 ・ 飛 歩 銀 ・ ・ ・ 歩|六 | ・ 歩 角 ・ 歩 歩 歩 歩 ・|七 | 香 ・ ・ ・ 金 ・ 銀 王 ・|八 | ・ 桂 ・ ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=0 △8四飛まで
一方で飯島流では、△3四歩と突かず△3二銀から△3一角と引き、さらに5三または6四に角を出て玉の移動経路を作ることで、振り飛車と同じ平美濃に組むことができます(第2図)。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・v金 ・v桂v香|一 | ・v飛 ・v銀 ・ ・v銀v王 ・|二 |v歩 ・v歩v歩v角v歩v歩v歩 ・|三 | ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・ ・v歩|四 | ・v歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ 歩 銀 歩 ・ ・ ・ 歩|六 | 歩 歩 角 歩 ・ 歩 歩 歩 ・|七 | ・ ・ 飛 ・ ・ ・ 銀 王 ・|八 | 香 桂 ・ 金 ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=0 ▲3八銀まで
藤井システムと角交換振り飛車を避けられる
平美濃囲いのメリットは、文字通り美濃囲いが平らで低いので玉頭に争点を作らずにすみ、したがって玉頭からの仕掛けを長所とする藤井システムを相手にしないですむことです。
また、角交換されることがないので角交換振り飛車を避けることもできます。
飛車と角による飛車先速攻
飯島流は、△3二銀〜△5四歩〜△3一角のたった3手で8六の地点を角でにらむことができるのが特徴です(第3図)。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金v王v金v角v桂v香|一 | ・v飛 ・v銀 ・ ・v銀 ・ ・|二 |v歩 ・v歩v歩 ・v歩v歩v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・ ・ ・|四 | ・v歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 角 歩 歩 歩 歩 歩 歩|七 | ・ ・ 飛 銀 ・ ・ 王 ・ ・|八 | 香 桂 ・ 金 ・ 金 銀 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=0 △3一角まで
同じく引き角を特徴とする鳥刺し戦法(嬉野流からの派生形含む)では、△4二銀〜△5三銀が必須のため引き角の角筋を左銀がさえぎっているのに対し、飯島流では常に角筋が通っていて△8六歩からの仕掛けの権利があります。
したがって、振り飛車側は後述の通り序盤の駒組みに注意を払う必要があります。
持久戦狙い
飯島流引き角戦法は、上に書いたような飛車先速攻を狙える形ですが、実際に仕掛けられるのは振り飛車側が隙を見せた場合です。戦法としては持久戦に属するものと言えるでしょう。
もともと飯島流は、藤井システムを食らう居飛車穴熊以外で、安全に堅く囲える戦法で戦いたい、という発想で出てきた戦法です。まずはしっかり平美濃囲いに囲い切りたい、というのが飯島流を採用している方々の思いのはずです。
そしてもっと玉を堅めることもできます。例えば、△4四歩(振り飛車の角筋を遮断するのが先)〜△3四歩と突いて普通の高美濃囲いや銀冠に。飯島流らしい囲いとしては平美濃穴熊(参考2図。右銀を6二→5一→4二→3一→2二と移動)もあります。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・ ・ ・v金 ・v桂v王|一 | ・v飛 ・ ・v金 ・v銀v銀v香|二 |v歩 ・v歩v歩v角v歩v歩v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・ ・ ・|四 | ・v歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩|五 | ・ ・ 歩 銀 歩 歩 歩 ・ ・|六 | 歩 歩 角 歩 ・ 金 ・ 歩 ・|七 | ・ ・ 飛 ・ ・ ・ 銀 王 ・|八 | 香 桂 ・ ・ ・ 金 ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=0 △2二銀まで
飯島流引き角戦法対策
しっかり平美濃に組み上げるのを狙いとしている飯島流。これに対して三間飛車側は、仕掛けの権利を作っておくのが得策です。
角道オープン+▲5七銀型
それに適した形が、角道オープンの▲5七銀型、さらには▲6六銀型です(再掲載第1図)。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・v金v王v桂v香|一 | ・v飛 ・v銀 ・ ・v銀 ・ ・|二 |v歩 ・v歩v歩v角v歩v歩v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・ ・ ・|四 | ・v歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ 歩 銀 歩 ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 角 歩 ・ 歩 歩 歩 歩|七 | ・ ・ 飛 ・ ・ ・ 王 ・ ・|八 | 香 桂 ・ 金 ・ 金 銀 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=0 △3一玉まで
もともと飯島流に対しては対局開始直後に角交換を拒否する▲6六歩を突く必要性がないため、問題なく角道オープン型を選択できます。
第1図を見て、▲6六銀型のおかげで後手の角の頭にプレッシャーがかかっているのがおわかりでしょう。いつでも▲5五歩と仕掛ける権利があります。一方で▲6六歩型だと攻め味が劣ります。
石田流も狙える
▲6六銀型にはもう一つメリットがあります。それは、銀の利きのおかげで▲7五歩と突けることです(第4図)。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・v金v王v桂v香|一 | ・v飛 ・v銀 ・ ・v銀 ・ ・|二 |v歩 ・v歩v歩v角v歩v歩v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・ ・ ・|四 | ・v歩 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ ・ 銀 歩 ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 角 歩 ・ 歩 歩 歩 歩|七 | ・ ・ 飛 ・ ・ ・ 王 ・ ・|八 | 香 桂 ・ 金 ・ 金 銀 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=0 ▲7五歩まで
これにより、石田流を目指すこともできます(参考3図)。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・v金 ・v桂v香|一 | ・v飛 ・ ・ ・ ・v銀v王 ・|二 |v歩 ・v歩v銀v角v歩v歩v歩v歩|三 | ・ ・ ・v歩v歩 ・ ・ ・ ・|四 | ・v歩 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ 飛 銀 歩 ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 桂 歩 ・ 歩 歩 歩 歩|七 | ・ ・ ・ 角 ・ ・ 王 ・ ・|八 | 香 ・ ・ 金 ・ 金 銀 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=0 ▲7七桂まで
将棋ソフトお墨付きの布陣
なお、将棋倶楽部24に常駐している最強の振り飛車党コンピュータ将棋ソフト、Hefeweizen(通称「白ビール師匠」)が先手の棋譜約7000局に対し局面解析をしたところ、先手三間飛車VS後手飯島流でヒットした12局すべてでHefeweizenは角道オープン+▲5七銀型を採用していたので、将棋ソフトお墨付きの布陣と言えます。

駒組みの注意点
ただしこの角道オープン+▲5七銀型に組むときに注意点が2点ありますのでご注意ください。先に結論を言ってしまうと、▲3八玉型にしてから▲5六歩〜▲5七銀としましょう。
注意点1:▲5九玉+▲5七銀はNG
玉を移動する前に▲5六歩〜▲5七銀の形(参考4図)にしてはいけません。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂v銀v金v王v金v角v桂v香|一 | ・v飛 ・ ・ ・ ・v銀 ・ ・|二 |v歩 ・v歩v歩 ・v歩v歩v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・ ・ ・|四 | ・v歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ 歩 ・ 歩 ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 角 歩 銀 歩 歩 歩 歩|七 | ・ ・ 飛 ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 | 香 桂 ・ 金 王 金 銀 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=0 ▲5七銀まで
以下、△8六歩▲同歩△同角▲8八飛△7七角成!(参考5図。これが王手になるのが居玉の弱点)▲同桂△8八飛成で終了です。
後手の持駒:角 歩 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂v銀v金v王v金 ・v桂v香|一 | ・v飛 ・ ・ ・ ・v銀 ・ ・|二 |v歩 ・v歩v歩 ・v歩v歩v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・ ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ 歩 ・ 歩 ・ ・ ・ ・|六 | 歩 ・v馬 歩 銀 歩 歩 歩 歩|七 | ・ 飛 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 | 香 桂 ・ 金 王 金 銀 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:歩 手数=0 △7七角成まで
注意点2:▲4八玉+▲5六歩+▲6八銀はNG
また、▲4八玉+▲5六歩+▲6八銀の形(参考6図)もNGです。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂v銀v金v王v金v角v桂v香|一 | ・v飛 ・ ・ ・ ・v銀 ・ ・|二 |v歩 ・v歩v歩 ・v歩v歩v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・ ・ ・|四 | ・v歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ 歩 ・ 歩 ・ ・ ・ ・|六 | 歩 歩 角 歩 ・ 歩 歩 歩 歩|七 | ・ ・ 飛 銀 ・ 王 ・ ・ ・|八 | 香 桂 ・ 金 ・ 金 銀 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:なし 手数=0 ▲5六歩まで
この瞬間にやはり△8六歩とされ、以下▲同歩△同角▲8八飛に△8七歩!が習いある頻出の手筋で、▲同飛に△7五角!(参考7図)が激痛です。
後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂v銀v金v王v金 ・v桂v香|一 | ・v飛 ・ ・ ・ ・v銀 ・ ・|二 |v歩 ・v歩v歩 ・v歩v歩v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・ ・ ・|四 | ・ ・v角 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ 歩 ・ 歩 ・ ・ ・ ・|六 | 歩 飛 角 歩 ・ 歩 歩 歩 歩|七 | ・ ・ ・ 銀 ・ 王 ・ ・ ・|八 | 香 桂 ・ 金 ・ 金 銀 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:歩二 手数=0 △7五角まで
王手なので仕方のない▲7五同歩に△8七飛成でやはり後手優勢となります。なお、▲2二角には△1二飛があります。
無事▲5七銀型に組んだ後の三間飛車の戦い方の紹介は、本記事では割愛します。また別の記事で解説するかもしれません。
飯島流関連の棋書
飯島流引き角戦法を解説する棋書は、2020年4月時点で飯島栄治七段が執筆した4冊があります。
3冊目の「対振りの秘策 完全版 飯島流引き角戦法」は、1冊目の「飯島流引き角戦法」と2冊目の「新・飯島流引き角戦法」の2冊を1冊に合本したものです。
2冊目の「新・飯島流引き角戦法」には先手三間飛車対策が、4冊目の「堅陣で勝つ!飯島流引き角戦法 Final」には後手三間飛車対策が載っています。
三間飛車目線で飯島流対策を解説する棋書は、私の知る限りありません。
これは、三間飛車にとって飯島流は恐るるに足らず、という意味ではなく(四間飛車より三間飛車の方が飯島流と戦いやすいという感触はありますが)、単に飯島流が主流ではないため飯島流対策解説書のニーズが少ないからだと考えられます。
特殊感覚の対振り飛車戦術
角道を開けず、振り飛車と同じ平美濃囲いに組みに行く飯島流引き角戦法。玉頭に争点がなく、通常の居飛車戦術とはかなり感覚が異なっています。
三間飛車側としては、完全に無策でいるといつの間にか相手に玉をガチガチに堅められて苦労することになるかもしれません。
角道オープン+▲5七銀型、さらには石田流に構えるなどして5筋や7筋に争点を作り、いつでも強く戦っていける方針をとると良いでしょう。

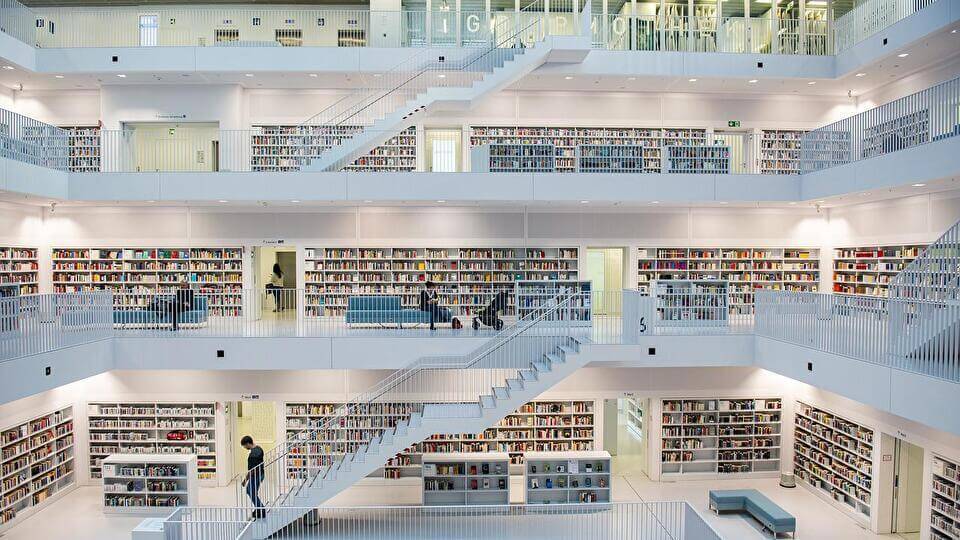
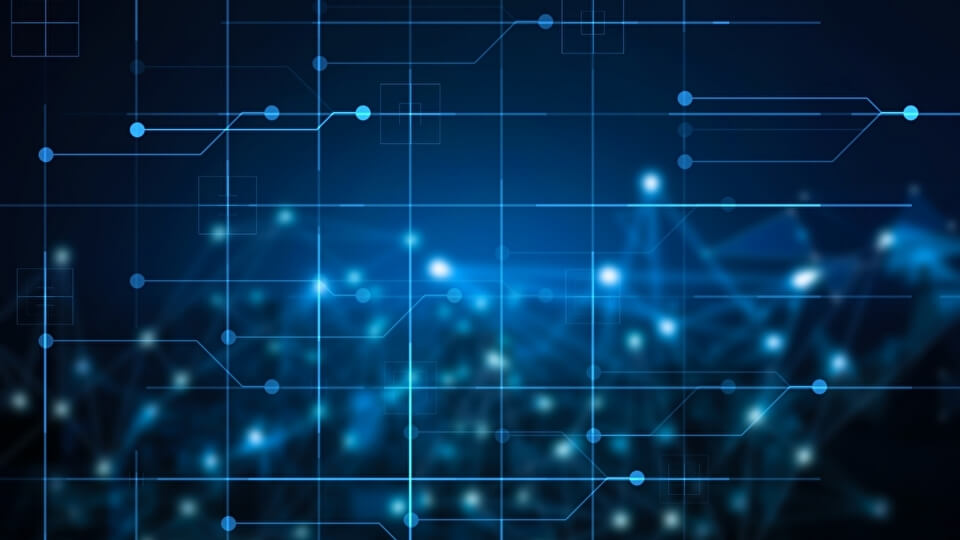
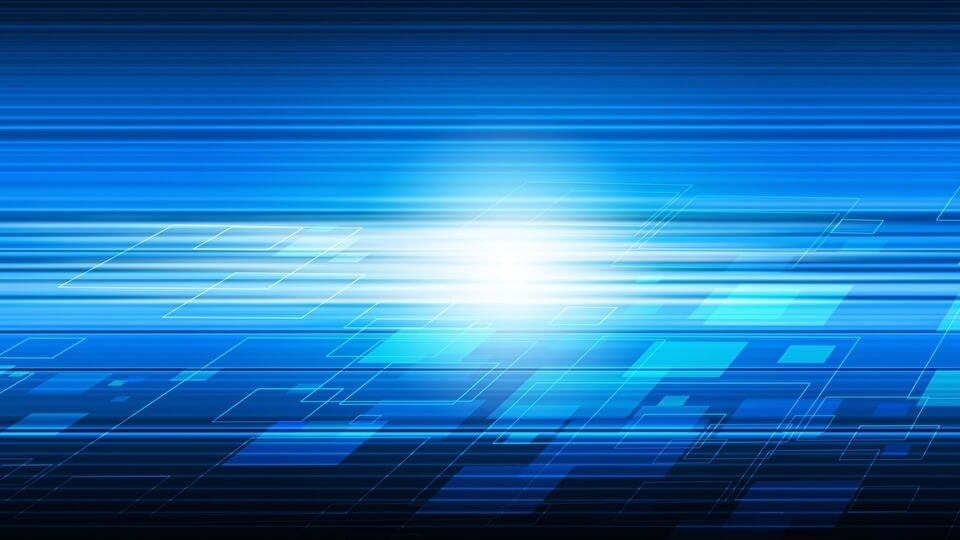
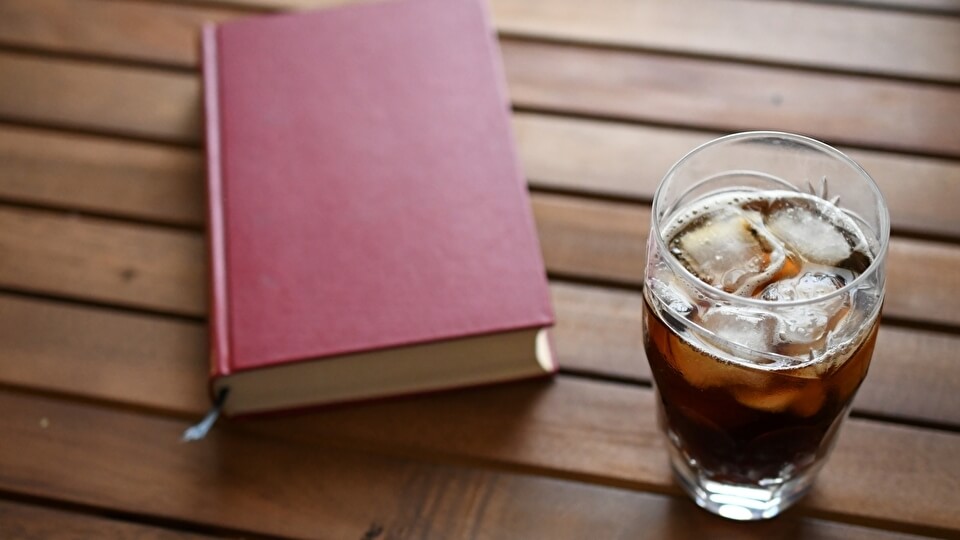









コメント